![]()
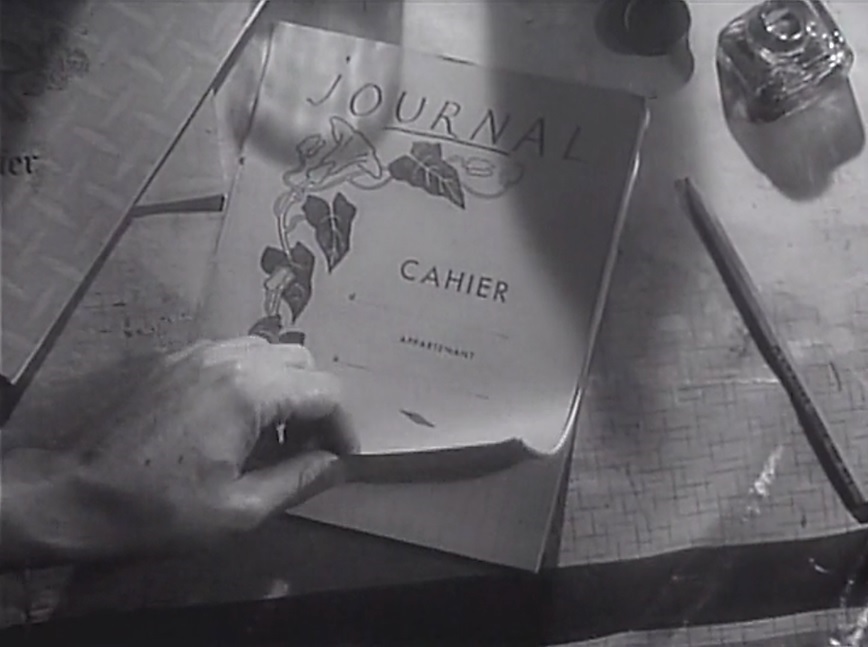
前回 ( 上記 ) の記事 ( 2022 / 03/22 ) からの続き。

3章 信仰と自由意志

伯爵の娘シャンタルは、家庭教師のルイーズが父親と浮気しているのが許せずに殺してやりたいと司祭に打ち明ける ( 11~14 )。ここで注意すべきは、司祭が、彼女の憎しみの気持ち自体を由々しきものとして否定するのではなく、神の前でそのような告白する行為 に驚く、という事です。それはシャンタルの母親との会話 ( 15~34 ) の内容に繋がっていくものとなっています。

シャンタルの気持ちを知って、母親である伯爵夫人のもとに来た司祭 ( 15~18 )。もちろん、これはたんなる家庭内不和を解決しようというのではなく、夫人の内面の告白を聴こうとしてにものです。そこで驚くべきは、最初は夫の浮気に対して何食わぬ顔を装っていた夫人ですが、実は内面において娘と同じく "憎悪" の気持ちを抱いていた という事です。そして夫人のこの憎悪は、このような状況に直面させた神へと向けられていく。

自分をこのような状況に陥っている事の苦しみを神への憎悪として感情的に表す夫人に対して、その過ちを説く神父 ( 20~22 )。


しかし、この辺りから、神父の心境に微妙な変化が現れてくる。神に憎しみを抱いた夫人に実は共感していた事を仄めかすのです ( 27~30 )。その上で最後に心の平安を説いて夫人を落ち着かせる ( 31~34 )。神に身を委ねるというアウグスティヌス的説法 ( 23 ) からもっと "自由意志的行動" に基づいた平安を説く事へとその内容を秘かに変化させているのです。まるでアウグスティヌスとその教義において対立する ペラギウス に肩入れするかのように。


哲学的に考えるのならば、アウグスティヌスは人間存在の根幹に "原罪という出来事" を組み込んで、人間主体はそのような出来事の中で誕生しているからこそ、それは神の恩寵を必要とする生き物だという神学的 ( あるいは精神分析家的な ) 縛りを強力に築き上げた。もっと細かく言うと、彼は人間における自由意志それ自体を否定しているのではなく、自由意志に任せるがままにしておく事が 悪の道へと傾斜してしまう のを危惧している。だからこそアウグスティヌスは、自由意志の無差別的な壊乱性 ( それはまさに悪にも善にもなりうるというペラギウスの自由意志論なのですが ) を制限して、信仰こそが人間を神の恩恵へと関わらせるという "善の選択行為” 、すなわち、 "自由意志的な行為" の最も優れたものである と書き換えたのです。
一方、ペラギウスは人間を神に従属させる "神の臣民主体" として制限するアウグスティヌスに対して、信仰という行為の実践性 こそが人間を1人の "個人" として確立させる上で必要な自由意志の領域を、ギリシャ哲学的個人主義 の側面から尊重していた といえるでしょう ( *E )。ここで司祭はその内面的立場において、アウグスティヌスとペラギウスの間で揺れ動いている。アウグスティヌスに従うならば、信仰とは自らをキリスト教秩序の中に収めるよう規律化させる 従属性に沿った主体的行為 となる。対してペラギウスは、人間を何らかの制度や組織に従わせる権力的秩序的行為 ( 人間を宗教的主体にさせる事 ) によってその存在を保障するのではなく、純然であるが故に脆くもある "個人" ( それは権力を振い、権力に従う "主体" とは違う ) として世界の中に確立させる道徳行為 として信仰を位置付ける。
( *E )
以上のように書くと、アウグスティヌスは人間の自由を奪おうとする権威主義的宗教家なのかと思う方もいるかもしれませんが、一概にそうは言えないのです。彼はある意味で 悪を逆説的な意味で評価している とさえいえるのです、自らの経験 ( 例えば彼の自伝『 告白 』を参照 ) も踏まえた上で 悪の力を見くびっていない という意味において。
悪を善と対立させる図式 ( そのような図式は 善が悪の後でしか現実には生まれない概念である事 を実は示唆している ) 以前に、人間存在が既に悪の力にとり憑かれ魅了されている事をアウグスティヌスは分かっている。それどころか標準的神学理解を越えて、人間における自由意志の発生それ自体が悪の力に負う部分が多い狂気的なものだ という事をアウグスティヌスは無意識的に理解していた。その意味で彼は古代の精神分析家であったとも解釈出来るのです。

4章 自由意志と死

しかし、司祭のこの揺れ動きが危険かつ必然的であるのは、自由意志の極限的行使が、神の加護を受けた 霊魂の永遠性 という 超越論的架空の視点 ( なぜなら宗教は死後には全てが "無" に帰すとは説かないから ) に人間を立たせ、肉体的死 の方へと積極的に向かわせてしまう からです ( それは 殉死 によって示される )。どれ程、肉体的死がたんなる "無" へと至る消滅でしかないという現実 ( あの世があるというのは宗教的主体に与えられる慰めしかない ) を頭で理解していても、"霊魂" という概念 によって、現世なものの究極的物質化である肉体に制限をかけ否定さえするという教説がイデオロギーとして歴史的に具現化されてきた事実 が漠然とした形で司祭を悩ませるのです ( この辺のニュアンスはキリスト教やフランスの歴史にについて語る原作でないと伝わらないのですが )。
ベルナノスの原作を細かく読めば分かるのですが、司祭が自らの信仰に確信を持てずに苦悩するのは、現世的快楽に目が眩んでいるからなどという単純な理由によるのではなく、信仰それ自体の現実的根拠が霊魂の永遠性という超越論的架空点に支えられた 権力的教説ではないか、つまり、信仰への情熱故に孤独に浸る司祭の内面において、真に個人的であるとは一体どういうことなのか、信仰という宗教的権威に関わる行為はもしかしたら それを教えてくれる事はないのではないか、という論理的疑念が漠然として形で働いているからなのです。
このような司祭の内面に蓄積された疑念が、同じく神への信仰によっても自分の内面の葛藤を抑えきれない伯爵夫人に 自殺による魂の平穏 を無意識的に示唆してしまう ( 肉体的に死んでも魂は永遠なのだからという建前を皮相的に投げかけている ) という決着を出現させる。この司祭と伯爵夫人の宗教的対話の場面 ( 15~34 ) が重要でありながらも分かりづらく、かつ恐ろしいのは、次のような複雑な構図によるからです。司祭は、魂の永遠性というイデオロギー的教説が虚構であるかもしれないと薄々思いつつも、家族関係で思い悩む伯爵夫人に対してこの世への執着こそが苦悩の原因なのだから現世的なもの象徴である肉体を消滅させて魂の永遠性の中に平穏を求めよと仄めかす。夫人の方も司祭の説教が皮相的なものだと分かった上で、ならば私はあなたの説教を "敢えて" 文字通り本気で受け止める、その教説を極限化させ自殺する事によって証明する。その上で、あなたにとって "魂の永遠という教説" が引き起こす現実がいかなるものであるのか、あなたの中に何かを引き起こすのか、あなた自身に返そう と言っている。つまり、夫人は一旦は揺らいだ神への信仰をについての確信をこの会話中において自分自身の力で取り戻す。そして、では同じく信仰に不安を抱える司祭はどうなのかと投げかけている訳です。
やがて彼女が口を切った。「 わたくしが赴くのはあなたのもとにです。 ― わたしのもとに!― ええ、あなたのもとに。わたくしは神にそむきました。神を憎まずにはいあられませんでした。そうです。いま考えれば、わたくしはこの憎しみを心に抱いたあっま死ぬところでした。でもわたくしは、あなたのもとにだけまいります。〈 中略 〉。― いいえ、あなたにはおわかりになりません。あなたはわたくしがもうすっかり従順になったものと思っていらっしゃいます。でも、わたくしに残っている傲慢だけでも、あなたを地獄に堕とすのに充分なものでしょう!
ジョルジュ・ベルナノス「 田舎司祭の日記 」 『 ジョルジュ・ベルナノス著作集第2巻 』所収 渡辺一民 / 訳 春秋社 ( 1977 ) p.146~147
夫人は自死による心の平穏という選択とその選択を決意させた会話の中での神学的因果を神父に与え帰したのですが、それはまさに 神父の内面的苦悩の外的具現化とその回帰 なのです。つまり、夫人という他者に神父の苦悩が転化され、それを自らの苦悩であるかのように経験した彼女がその心境を神父に語るという迂回路は、神父と夫人の間で交わされた神学的会話の精神分析的構図に他ならない という事です。以下の ( 35~42 ) では、トロシーの司祭によって、そのような主人公の神父の夫人に対する発言はあたかも自殺を説く罪に値するものではないかと追及されている。


では神父は自分の発言が夫人の自殺のきっかけではないかと周囲から言われる事のついてどう考えていたのか? 原作では次のように司祭の心情が綴られている。
またわたしには、だれもわたしにたいして過度の厳格さゆえに ― 不正というような大袈裟な言葉は使うまい ー 罪人とはならなかったと思うこともじつにこころよい。なるほど、わたしは、自分が犠牲となった不公平についての意識のうちに、力と希望の根源を見出しうる霊魂を賞賛するのにやぶさかではない。だがどうしても、わたしは、自分が他人の過ちの ー たとえみずから潔白であろうとも ー 原因、あるいはたんなる機会だけにでもなったと知ることに、これからも耐えられないだろうと思う。
前掲書 p. 245~246
だから、ときにはわたしの受けた非難が、わたしのまことの運命についてのわたしたちおたがいの無知からのみなされたものだったと考えることは、わたしにとって大きなよろこびにほかならない。
前掲書 p. 246
わたしは人々をあるがままに愛した ( それにそれ以外に愛しようがなかったと思う ) 。この素朴さが、けっきょくのところ、わたしにとっても隣人にとっても危険なものになってしまう。それというのも、わたしはいつでも、打ち克ちがたく思ってきたわたしの心の自然な心の傾きに、じつに不器用にしか抵抗してこなかったからだ。
前掲書 p. 246
少しわかりにくかったかもしれませんが、司祭は確かに夫人の死について責任の一端を感じている。しかし、夫人に説いた言葉は決して積極的な自殺の教唆などではなく、普段から自分が死について考えている事が滲み出てしまったのだと釈明している訳です。では司祭が死について考えていた事とは何なのでしょう〈 続く 〉。
■ 次回 ( 下記 ) の記事 ( 2022 / 03/22 ) に続く。
