![]()
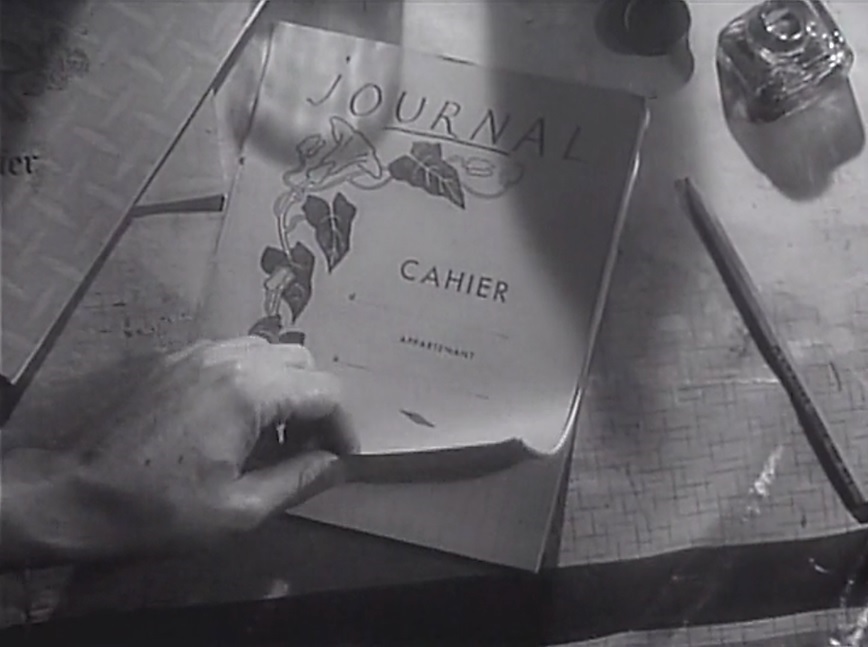
■ 前回 ( 上記 ) の記事 ( 2022 / 03/22 ) からの続き。

5章 愛としての死

司祭が死について考えていた事。それは司祭の内面の苦悩 ( 信仰への疑念 ) の帰結でもあったのですが、率直に言うなら、それは 死において愛が完成されるという信仰の究極の帰結 なのです。死という究極の孤独状態に人間が立つ時にこそ、愛が現れる、つまり、誰 ( 自分自身を含めて ) をも憎む事なく、不安になる事なく、恐れる事なく、自分を神の加護の下に置いて愛によって心を平安に導く消え去っていく。
司祭は十字架上のキリストが今まさに殺されようとしていう時に発したとされる言葉「 父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分がしていることが分からないのです ( ルカ福音書 ) 」を引き合いに出しながら愛について考える。
〈十字架 〉のうえで、苦悶のうちにその〈 聖なる人間性 〉を完成しようとなさったときでさえ、わが主はみずからを不正の犠牲者とは認められなかった。《 彼らはなすところを知らざるものなれば 》どんな小さな子供にもわかる言葉、子供らしいと言いたくなるような言葉、しかも悪魔が以後理解できぬまましだいに怖気づいて繰り返さざるをえなかった言葉なのだ。神の怒りの火のくだることを予期していたのに、悪魔のうえで深淵の入口をふさいだのはおさな子の無心の手だったのである。
前掲書 p. 246
けれども、わたしの臨終はなるようにならせるより仕方あるまい。いささか大胆かもしれないが、あえて言えば、どんなに美しい詩だって、ほんとうに恋しているものにとっては、口ごもった拙劣な告白の値打ちもないだろう。よく考えてみれば、こうした比較にだれも文句がつけられまい。人間の臨終はまず愛の行為にほかならぬからだ。
前掲書 p. 247
わたしが自分について、自分自身について抱いていた一種の疑惑は、永久に四散したのだと思う。あの闘いもおわった。もうそれもわたしにはわからない。わたしは自分自身と、このあわれな脱け殻と和解したのだ。
自分自身を憎むことはそう思われているよりもたやすい。自分を忘れることは、清聴聖寵である。しかし、もしわたしのうちで傲慢そのものが死に絶えるとすれば、そのばあい、このうえもない聖寵とは、自分自身をイエズス・キリストの悩める肢体のどれでもいいひとつとして、つつましく愛することではあるまいか?
前掲書 p. 249
孤独の中にこそ現れる愛こそが真実の愛ではないか、そのような愛が現れるようにする事こそが信仰であり、人間が1人の個人としてその生涯を全うしたことを 最後の孤独の時間において慰められる事こそが信仰の真理であり、神の恩寵なのではないか、という事をベルナノスは司祭の生涯を通じて表現した。ただし、付け加えなけえればならないのは、この "死" をベルナノスは単なるキリスト教徒の静謐な人生の中に限定化するのではなく、それどころか "信仰、殉死、そして魂の解放というモチーフ" を以て、宗教を超えた人間の社会的在り方の方に向けて解放している、すなわち、死を人間社会を見つめ直す契機として社会的メッセージ、もっと極端に言うなら、ある個人の死が社会にとっていかなる意味や価値を持つのか考えるべきだ という "革命的メッセージ" を言外で訴えているのです。逆に言うとそれをどう考えるかでその社会の真実が見えてくるとも言えるでしょう。少なくとも、ベルナノスは、信仰こそが 個人という存在 に、最後の死の瞬間、絶望の瞬間に、どのような人生であれ意味があったことを教えてくれる 社会的なものだ と考えている。

6章 孤独と生

司祭の病死で以って物語の幕が下ろされる時に、その死が如何なる意味を帯びているのか、それは『 田舎司祭の日記 』が私たちに投げかけてくる問題です。実はそれを考える事は 司祭の死が原作と映画では意味がわずかに違う ( そこにブレッソンの考えが賭けられているが故に ) のが明らかにしてくれるし、同時にその差異は、バザンを始めとする映画批評、この作品を賞賛した人たちが、一見原作を持ち上げているようで実は大してそれについて考えず、映画を芸術として一方的に美学化していた事を露呈させるのです。
バザンが、原作と映画の単純には纏められない関係、原作への忠実性とその忠実さの極大化による新たな創造性の提示などのような緊張関係がブレッソンの作品にはあるとして、原作と映画の複合的美学化 に向かう時、実はバザンにみならず、この映画を賞賛した人々 ( ノーベル文学賞を受賞したフランソワ・モーリヤックなど ) が果たして原作をどこまで読み解いていたかは疑問なのです。
もし、バザンなどのような知識人が原作を "詳細に" 読んでいたならば、そこで描写される宗教的静謐性には宗教的領域には収まらない社会的・革命的メッセージが含まれているのを読み取り、その差異を問題にしてそこからブレッソンの作品を論じる事が出来たのではないか。もしくは差異がある事は分かっていても、それを拡大化して問題にすることはなかったのか。いずれにせよ彼にとって大事なのは 映画批評の美学化 であり、原作を詳細に論じることなど問題ではなかったのでしょう ( *G )。
個人的にはそのような方法論は別に構わないと思います。しかし、そうであるのなら文芸作品と映画を密着化させるような美学化などせず、ブレッソンは原作における革命的要素を排除し、創造的独断性に基づいた "自分の作品" を創り出したのだと率直に言う方がどれだけ原作と映画の両方に誠実であることか。正直な所、バザン ー トリュフォー 経由の作家主義という言葉にさえ、監督の独断的・独善的な政治性を芸術的用語でオブラートに包んだものに過ぎない権威的欺瞞性があると僕には感じられる。それは政治的な美学化に過ぎないのであり、個々の作品 ( どのジャンル・どの時代であれ ) を詳細に考える行為を骨抜きにするものでしかない。どの作家であれ、監督であれ、音楽家であれ、その人の世に出す作品の "全て" が擁護出来るとは限らない、どうしようもない作品もある、という事実はもうお分かりだと思う ( 例えばヌーヴェルバーグ作家の作品をとってみても )。美学化につきまとう全体的波及性は特権的な主体化と固有名化を生み出し個々の思考行為を抑圧する のです。
ここで話を戻しましょう。この映画を賞賛する人は、ベルナノスの原作から離れて何処に赴いたのか。それは余りにも紋切型な、信仰を巡っての余りにも人間的な苦悩の物語、司祭の内面的葛藤という主体の心理的領域内部での物語 なのです。これこそ、フランソワ・モーリヤック、ジュリアン・グリーン、グレアム・グリーン、などによって描かれたキリスト教信者が罪を巡って自身と内面的に対峙するという贖罪的モチーフ、信仰というものが、神に対する汚れた背信行為の中からでも立ち現れる宗教賛美的モチーフ、であり危機に陥りながらも人間概念の普遍性は結局は揺るがない "人間中心主義的なもの" なのです。
しかし、そのような視点からの讃美がブレッソンの望んだものだったのか。彼が装飾性を削ぎ落し、素人の俳優を使い、方法的演技を抑制させ、あらゆるものを静寂性の中に落とし込む時、それは信仰の禁欲さを表現しようとしたのではなく、信仰やその行為を関わる人間を超えて、それらを可能にしているものこそ "孤独" である事を哲学的に追求しようとしていた のではないか。孤独は信仰行為や人間の中にあるという常識的観念を超えて、孤独の中にこそ信仰や人間を含めた生の真実が現れる という脱人間中心的な考えに、ベルナノスの革命的人間観、つまり、自分という主体が消えた後でも、生は残り続ける ( ベルナノスの場合は解放された魂という形式で ) という "人間不在の生"、を引き継いだのではないか。
ベルナノスにおいて人間の生が宗教的領野に未だ囚われているのを超えて、ジャック・デリダ的に言うなら現前的なものの支配を超えて、特権的な何者かの中には汲み尽くされない 不在の生の圏域が、誰に対しても動物に対しても ( バルタザール!) 開かれたものとしてある ことを示そうとしたブレッソンは、孤独が生に付き添い、生の姿を顕させるものである事を独りの人間として理解していたのかもしれません〈 終 〉。
( *G )
ブレッソンの『 田舎司祭の日記 』の中に引き継がれたベルナノスのカトリック的な革命的人間観に気付いたのがアメリカの映画監督・脚本家 ポール・シュレイダー。彼はその著作『 聖なる映画 ー 小津、ブレッソン、ドライヤー ( Transcendental Style in Film : Ozu, Bresson, Dreyer ) 』の中でブレッソンの『 田舎司祭の日記 』に触れ、古代キリスト教司祭の神学論を参照しつつ殉教や魂の解放といった概念に言及している。ただし、そこでは、それらの概念で以って社会に対する革命的メッセージだとまでは言い切ってはいない。むしろその理解は彼の映画製作において具現化されていて、明らかにそのメッセージを受け取っているといえる …… のですが、それはほとんど 個人的テロリズム に近い歪んだ形で表わされている。脚本を務めたマーティン・スコセッシの『 タクシードライバー ( 1976 ) 』、三島由紀夫の自決を描いたいわくつきの作品『 Mishima: A Life In Four Chapters ( 1985 ) 』、そして『 魂のゆくえ ( 2017 ) 』など。ちなみに『 魂のゆくえ 』という邦題タイトルを原題『 First Reformed 』とは変えているのは、おそらく担当者がシュレイダーの『 聖なる映画 』で「 田舎司祭の日記 」に言及している箇所を念頭に置いているからだと思われる。
