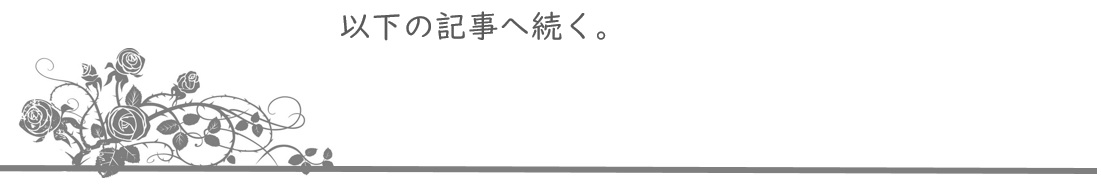![]()
![]()
![]()
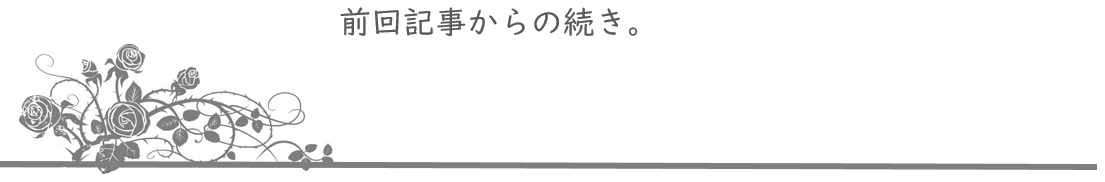
![]()
CHAPTER 3 ドイツ的政治性を帯びたガブリエルのイスラエル擁護
![]()
![]()
1. 今回の記事で何よりも気になるのは、記事の最期で戦争に巻き込まれる一般のパレスチナ人を憂慮すると言いながらも、実際にはそこまで気にしてはいないのではないか、彼が気にしているのはイスラエルの人びと及びユダヤ人の方なのではないか、という点です。これはパレスチナ人の方がどう、いやユダヤ人の方がどうだ、という話ではなく、戦争に巻き込まれる人々というのは、どちらであれ戦争の犠牲者である事には変わりないのだから、普遍的な人間性の観点からすると戦争それ自体に反対するのが哲学者の役割のはずではないか、という事です。
![]()
2. ガブリエルがどちらかの当事者国の人間であるのならば、どっちつかずの立場ではいられないというのもまだ分るのですが、そうでない彼がイスラエル擁護の立場を表明する事に哲学者としての意味があるのでしょうか ( そのようなイデオロギーの表明は既に当事国の政治家・軍人・抵抗者によって為されているのですから )。 そこで彼は反ユダヤ主義及びテロリズムに反対する為だと言うのですが、彼の間が抜けているのは、現在の世界情勢において反ユダヤ主義及びテロリズムに反対する事は必ずしもイスラエル側に就く事を意味しない のを理解出来ない所です。それどころかどちらかに一方的に就く事こそが反ユダヤ主義・テロリズムの強化・暴走に繋がってしまうのです ( *1 )。
![]()
3. イスラエルの軍事行動に反対しながらも、反ユダヤ主義・テロリズムにも反対するという並列関係の緊張的維持 こそが、暴力性への同一化・単一化現象の普遍化を防ぐ真のパラタクシスであり、そのアドルノの概念の真の政治的有効転用、なのです。このような立場は既にプリーモ・レーヴィやジュディス・バトラーが唱え、そして最近のスラヴォイ・ジジェクが採るもの ( このような主張によって彼は一部のイスラエル擁護者から批判される羽目になっているのですが ) となっています。
![]()
4. そうすると、ガブリエルのイスラエル擁護については、第一にはそれはホロコーストによってユダヤ人を迫害したドイツのイスラエル国家保護の政治色 ( ユダヤ人への贖罪表明や軍事兵器の積極的輸出、等の歴史的経緯が絡み合った複合的なもの ) が余りにも硬直化した結果によるものだといえるでしょう。イスラエルに反対する者は反ユダヤ主義に他ならないとするこの短絡的傾向 が現れた出来事が少し前のドイツであったのですが、次章で考えていきましょう。
![]()
( *1 )
例えば、新聞記事ではガブリエルは敵対勢力のハマスをテロリストとして非難するが、この場合、これはイスラエル視点からの呼称に過ぎないのであって、パレスチナ側からするとイスラエルもこれまでに、ユダヤ人武装組織イルグンによる1948年のデイル・ヤシーン村のアラブ人住民の虐殺のようなテロ行為に等しい事件を起こしている。エドワード・W・サイードは当時のイルグンを率いた、後のイスラエル首相となるメナへム・ベギンをテロリストだと名指しさえしている。このように "暴力性" は、既に片方の反ユダヤ主義やテロリズムに固定的に留まる状態を超え出て、双方の対立を激化させる "最悪の普遍的現象" と化している事 を歴史は示している ( だからこそイデオロギーを超えて、戦争・暴力 "それ自体" に対して反対しなければならないのですね )。
ベギンは長年に亘ってテロリストとして鳴らし、その事実を隠そうともしなかった。彼の著書 『 叛乱 』 は、標準的な中東文献コレクションの一環として、大学図書館や中規模の公共図書館ならどこにでも収蔵されている。同書中でベギンは、自分のテロ活動を - 罪もない女性や子供たちの無差別大量虐殺も含め - 当然のことのように ( ぞっとするほど ) ふんだんに叙述する。一九四八年に四月に発生した、あのデイル・ヤースィーンのアラブ村落での二百五十人の女性・子供虐殺事件についても、彼は自分に責任があることを認めている。〈 中略 〉。 だが、イスラエルの指導者は民主的・西洋的で、通常アラブやナチス ( それらは結局、イスラエルが自らの存在によって否定したものとして見做されている ) と結びつけられる悪徳に耽ることなどできないとする含意があまりに強いため、ベギンのように普通なら消化し難い一破片ですら、ひとかどの政治家へと変質させられてしまう ( そして、一九七八年には、ノースウェスタン大学から名誉法学博士号を取得、挙句の果てにはノーベル平和賞まで授与された ! )。
『 パレスチナ問題 』 エドワード・W・サイード / 著 杉田英明 / 訳 p. 63~64 みすず書房 ( 2004 )
![]()
![]()
![]()
CHAPTER 4 反ユダヤ主義的と評されたアダニヤ・シブリーの 『 Minor Detail 』
![]()
![]()
1. ドイツのフランクフルトで毎年10月に開催される世界最大の本の見本市、フランクフルト・ブックフェアというものがあるんです。各国の出版状況が見えるブース出展、文化イベント、文化展示会、各国出版社間での版権の売買交渉、各種式典、等が数多くの来場者と共に形作られる巨大イベントです ( 2023年は10月18~22日開催 )。その2023年のフランクフルト・ブックフェアにおいて英語圏・ヨーロッパ語圏以外の文学を翻訳紹介するドイツの文学協会LitPromによって創設された、非英語圏・非ヨーロッパ語圏の女性作家に与えられる LiBeraturpreis ( リベラトゥール賞 ) の授与式が開催数日前になって突然中止発表されるという事態が起きました。
![]()
2. リベラトゥール賞の受賞予定者はパレスチナ出身の女性作家 アダニヤ・シブリー ( Adania Shibli ) だったのですが、その彼女の作品 『 Minor Detail ( アラビア語表記 : تفصيل ثانوي タスフィール・サーナウィー ) 2017 』 が反ユダヤ主義的だと評してLiptomの審査委員を辞任したジャーナリストの Ulrich Noller、Süddeutsche Zeitung紙で同作品をパレスチナ人に対するレイプ及び殺害を行なったイスラエル兵数人を名前も顔もない者として描いた事で単なる反ユダヤ主義を煽る象徴化にしか行き着いていないと批判した作家の Maxim Biller 、そして、この両者の発言を引き合いに出しながら、"テロリストのハマスによる大量殺人の後では賞の授与はほとんど耐えがたいものになるだろう ( Nach den Massenmorden der Hamas-Terroristen aber wäre die Preisvergabe kaum auszuhalten. )" との記事 ( 2023年10月10日付 ) を掲載したTageszeitung紙 ( 通称Taz紙 )、これら一連の作品批判によって賞の授与は中止されたという訳です。
![]()
3. ユダヤ人であるイスラエル兵の残虐性を、"歴史的事実"に依拠する事でクローズアップするような象徴的記述化は反ユダヤ主義を助長するものでしかないというこれらの批判には一見すると正当な言い分が含まれているかのように思えるかもしれません。しかし、そうではありません。それらの言い分は全く文学的なものではなく、文学的考察からは離脱した"非文学的言説"、つまり、"政治的イデオロギー"で批判するものでしかないのです。
![]() 4. たしかに『 Minor Detail 』は、1949年8月にイスラエル国防部隊の兵士によるベドウィン系パレスチナ人少女の強姦及び銃殺行為という、2003年に明るみになるまで隠され続けて来た忌まわしい事実 ( ここで事実と言うのは、この事件に関わった者たちが当時の軍事裁判で裁かれている事による ) を物語りの発端・契機 ( ただし、それはこの作品の哲学的真理ではない ) として描いている。この忌まわしい事実がイスラエル首相であったベン=グリオンの日記に書き残されていたという事及び、その彼の記述がイスラエル国家にとって不都合な箇所であるとして隠されてきたという事は、ユダヤ人が被抑圧民族であるというこれまでの歴史的・政治的定型を壊しかねないものだ と彼ら自身が考えていた事を露にしている。
4. たしかに『 Minor Detail 』は、1949年8月にイスラエル国防部隊の兵士によるベドウィン系パレスチナ人少女の強姦及び銃殺行為という、2003年に明るみになるまで隠され続けて来た忌まわしい事実 ( ここで事実と言うのは、この事件に関わった者たちが当時の軍事裁判で裁かれている事による ) を物語りの発端・契機 ( ただし、それはこの作品の哲学的真理ではない ) として描いている。この忌まわしい事実がイスラエル首相であったベン=グリオンの日記に書き残されていたという事及び、その彼の記述がイスラエル国家にとって不都合な箇所であるとして隠されてきたという事は、ユダヤ人が被抑圧民族であるというこれまでの歴史的・政治的定型を壊しかねないものだ と彼ら自身が考えていた事を露にしている。
![]()
5. ベン=グリオンの日記の秘匿されてきたパレスチナ人少女の殺事件 ( この事件以外にも隠されている政治的箇所は幾つもある ) は2003年にイスラエルのリベラル紙『 HAARETZ 』によって明らかにされたのですが、シブリーの『 Minor Detail 』はこの史実の延長上において、その事件を政治的事実としてイデオロギー的主張 ( パレスチナ人の生存権のような ) の為に利用したのではありません ( ドイツの批評家たちがその点において『 Minor Detail 』を批判したのは誤りでしかない )。そうではなく、その事件が現在では政治的記録として以外は残されていないイデオロギー的事後固着性とは違う"視点"で、シブリー自身の一人称の "虚構視点" の意図的使用で以って、この事件、この暴力性、を日常生活・日常風景の中に置き直す、つまり、政治的イデオロギーでは排除され打ち捨てられてしまう日常的細部のついての語り ( そこにおいて『 Minor Detail 』というタイトルの意味が生きてくる ) の中で暴力性を捉えなおす、このように日常性を脅かす暴力の不穏性を淡々と描く事で、読む者にイデオロギー的立場を越えた暴力性についての現在的反省をもたらすのです ( この淡々とした筆致こそが、暴力描写の場面において、一部の批評家にホラーのようだと誤解させているのですが )。
![]()
6. さらに、ここで考えておかなければならないのは、上でも述べた作家の Maxim Biller の批判、とそれを引用したTaz紙の記事における、作中のイスラエル兵には名前も顔もないという批判には、はっきりとは述べてはないものの、ユダヤ人を顔の見えない残虐な行為者として象徴化させようとしているのではないかという含みがあり、『 Minor Detail 』を全く政治的にしか読み取ろうとしていない ( もしくはそれ以外には出来る能力が無いというべきかもしれない ) のに本人たちが気付いていない事です。
![]()
Maxim Biller は同じ作家であるはずなのに、作品をそれ自体において ( 作品として ) 捉える事が出来ず、自らの出自であるユダヤ人である事及びシオニストである事のイデオロギー立場にこだわり『 Minor Detail 』を政治的にしか語れないのだから、彼の文学観は "現実に秘かに依拠する" だけの貧相なものでしかない。そう考えさせる文学事件、彼の小説『 Esra ( 2003 ) 』が彼と現実の人間関係にあった母娘の二人から自分たちをモデルにしたと訴えられドイツの裁判所から発禁処分を受けるというスキャンダルな事件、がかつてあったんですね。
![]()
もちろん、文学作品の自由や権利を考慮すれば問題のある判決なのですが、それとは別にその事件は彼の創作の秘密が、自分自身の思考からではなくたんなる現実に依拠・従属するだけの貧相なインスピレーションに過ぎなかった事を露呈させてしまったといえるでしょう。それは、アンドレ・ブルトンが『 ナジャ 』において実在の女性を "超-不在" という形式で固有名化 ( ナジャ ) する事で作中に持ち込んだようなものであり、それは結局の所、彼がアントナン・アルトーのように自らの中で思考 ( シュルレアリスム等の ) を深める事の出来なかった能力的限界から "現実の方へ逃避しているのに過ぎない ( それはブルトンの美学的装いで隠されている )" のとさほど変わらないのです。
![]()
7. このようなMaxim Billerらの批判、そして同時に、実話を参照している事を擁護してくれる意見、にも対してシブリーは真摯な思考で以って次のように答えています。
私の小説がイスラエル人に対する暴力を扇動しているとか、私が「熱心なBDS[イスラエルに対するボイコットなどをよびかける運動]活動家」であるといった、事実とは違うことを報じたのは taz紙の記者だった。リトプロム[ リベラトゥール賞主催団体 ]がそれに続き、彼らは当初、授賞式の中止は私と共同で決定されたことだと、事実と異なる表明をしたのである。「 事実でないこと 」、また文学上のフィクションは、現実世界には決してそんな影響を与えない。文学と現実世界との関りというものは、変化を煽ることではなく、物事との深い結びつきや内容を促すことにある。おそらくそれは、生きることから苦痛に至るまで、自分自身や他者との関わり方を考える場において、より良く生きる方法を想像する方向へと導くことである。
『 かつて怪物はとても親切だった 』 アダニーヤ・シブリー / 著 田浪亜央江 / 訳 p.10~11 文藝 2024年夏季号所収 河出書房新社 ( 2024 )
* 下線は引用者である私によるもの
しかし、その taz 紙批評家 ( と呼んでもいいのだろうか ) による中途半端に洗練された手法は、私がさらに考えるための手がかりを与えてくれた。彼の主張は、この小説に登場するイスラエル人レイプ殺人犯たちには、名前も顔もない、というものである。
中途半端に洗練された手法、とはこういうことだ。彼は自分のイデオロギー的見解を押し通すためにこの件を持ち出しているのだが、パレスチナ人全員を含む他の登場人物たちにもやはり顔も名前もないことを無視しているのである。彼はパレスチナ人の登場人物もそうだとは気づいていないのだろう。パレスチナ人に顔も名前もないのは、彼にとって当然のことだから。
そしてまさにこのことが、最新作だけでなく、私の書く文章のほとんどに、なぜこのような名前も顔もない登場人物が現れるのかについて、新たな理解を与えてくれた。私が親しんでいる文学的感性は、こうした無個性さと無名性によって特別にデザインされていることに気づいたのだ。パレスチナ / イスラエルやその他の場所で、パレスチナ人だけでなく、アラブ人全般との関係で、現実世界において支配的イデオロギーによって他のサバルタンとともにどのように表象されているかということに関し、この無個性さと無名性は私がこれまでの人生のなかでずっと遭遇してきたものだ。
前掲書 p. 11
* 下線は引用者である私によるもの
執筆活動をしてきたこの何年もの間ずっと、自分がなぜ無個性で無名の登場人物にしか親しみを感じられなかったのかについて、私は突然理解した。『 誰でもない者 』が文学で見出し、彼らが触発される文学のひとつの形式とは、魅惑的な不在であり、名前のない場所なのである。
別のドイツ人批評家 ( 引用者注:おそらく作家Maxim Billerを指している ) が、私の小説の結末について、誰の視点に立っているのか、これが物語の結末なのか、という疑問を抱いていることを知った。これは重要な問いであり、別のタイプの名前も顔もない登場人物、つまり幽霊に私たちを導くものである。名前も顔もない登場人物たちとは、文学上の幽霊以外の何者かでありうるだろうか?
だが、taz紙の記者にひとつだけ断言できることがある。いつか彼が私の作中人物の一人に息を吹き込んだとしても、それもまた顔のない、名前のない登場人物にしかならないだろう。
前掲書 p.11~12
* 下線は引用者である私によるもの
しかし、何人かのジャーナリストはこの小説を擁護するために、これが1949年にネゲブ砂漠でイスラエル兵にレイプされ銃殺されたベドウィンの少女の実話を参照していると指摘した。
私自身は、文学と現実とのあいだにそのような言及や関連付けをすることは控えている。小説の中の出来事が現実なのかフィクションなのかを問うことは、小説の中のテーブルや椅子が現実なのかフィクションなのかを問うことと同じようなものだ。小説は虚構の試みであり、関心を向けるのもまた虚構なのだ。
前掲書 p. 14
* 下線は引用者である私によるもの
現実には、言葉はしばしば、わかりやすく明確で合理的な語りという、ひとつの一般的な形式に押し込められる。しかし、もしそうする能力がまったくない場合、そのとき、どんな言葉が出現するのだろうか? 傷ついた、あるいは存在しない言葉を使って、どうやって書き始めるのか? 小説を書くようになる前、こうした疑問すべてが私を悩ませた。一方にあるのは、私たちが受け入れ可能な言語の物語形式をたどることであり、他方にあるのは、私たちがほとんどアクセスすることができず、おそらくアクセスしたいとも思わないために軽視する物語形式を語ること。科学捜査の言葉を使うなら、『 タスフィール・サーナウィー 』は、私たちが部分的に追跡可能な言葉の足跡をたどろうとすることで、文学的な形式を探求してきたと言える。この小説を書き終えた今、物語の構造や文体を含めて、その文学的形式と内容を導いた関心をよりよく理解できるようになった。これらはすべて、特定の言語的体験によって形成されてきた。要するに、現実の出来事と関連づけることは、一般的に私の文学を支える力ではないし、特に『 タスフィール・サーナウィー 』ではそうではない。
前掲書 p. 14~15
* 下線は引用者である私によるもの
![]()
8. 以上の引用から読み取れるのは、シブリーが『 Minor Detail ( タスフィール・サーナウィー ) 』で試みたのは、人々が文学において受け入れて来た "物語形式" を踏襲する事、さらにそこに、その物語が何らかの史実に基づいているかのような "現実性への接近" という追跡負荷を掛ける時、何が起こるのか という事なのです。そこで彼女が見出したのは、文学における言葉とは、ノンフィクションとは違い、人々が飛びつきがちな現実の方に近づく事で力を発揮するものではなく、現実の手前で、現実に取り込まれてその中へと消えてしまう手前で、言葉が自分自身の下で立ち戻り、自分自身の中へと入って行くような、誰かのものでありながら誰のものでもない "空白・深淵・場所 ( それはまさにシブリーが言う "パレスチナ" なのです )" から生まれる言語それ自体の現れ に他ならないという事なのですね。
![]()
9. 政治的イデオロギーが現実への依拠からその力を得るというのなら、シブリーはまさにその現実の手前で踏み止まりながら、言葉というものを現実を描写する道具的役割から解放し、言葉それ自体にあらゆるイデオロギーからの距離を保たせる "反省的次元 ( それこそが "Minor Detail" 、つまり、"ささやかな細部" なのです )" を導き入れようとする。そうする事で、イデオロギーにまみれた政治的当事者でなくとも、そうならずとも、世界の誰もが自由に "アクセスする / 訪問する" 事が出来る。そこには世界的普遍性に向かって開かれる契機があり、文学はまさにそれを可能にしてくれるという訳です。
![]()
10. さて話は長くなりましたが、次回でマルクス・ガブリエルがこの記事で露呈させた哲学的中立性の欺瞞について触れる事でこの話全体を締めくくる事にしましょう。
![]()