![]()

監督 : アッバス・キアロスタミ
公開 : 1999年
出演 : べーザード・トーラニー
: ファザード・ソラビ
![]()
1章 『 桜桃の味 』から『 風が吹くまま 』へ
![]()
『 風が吹くまま ( 1999 ) 』は『 桜桃の味 ( 1997 ) 』の続編だと考えられるだけでなく、さらに深化させたものだといえますね。この作品においてはアッバス・キアロスタミの思想がさりげなく示されているのですが、たんなる牧歌的な映画だとして受けて止めてばかりで何も考えようとしない人にとっては退屈な映画となるでしょう。
『 桜桃の味 』において映画の自己言及的描写 ( 当の作品を取る撮影状況の描写によって映画が唐突に締めくくられる ) によって中断された主人公の自殺というテーマが別の角度から、つまり、 死というものに対してどう接するべきなのか という事が描かれているのです。それは "死" に対する単純な生への礼賛ではないし、死を頭ごなしに否定するものではありません。貧富の差、人間関係の煩わしさ、など生きていくことの耐えがたさは、この作品でも描かれているのであり、そこから脱け出すことの困難さはキアロスタミも十分に分かっているのです。
注意すべきは、キアロスタミが、"死それ自体" を描こうとしているのではないという事です。死は人間 ( いや動物にも ) に訪れる "普遍的現象" なのですが、そこに至る個々人の心理的道程は様々であり、そこにおいては本人にしか分からない "個別的経験" が起きている。つまり、個別的でありながらも普遍性に至るという極めてヘーゲル弁証法的な極地に人は赴く のであり、そこでは人は個別的な物のままでいる事が物理的に出来ないという意味で、生きている者にとっては不可能な経験だといえるのですね。
ではキアロスタミはどのようなスタンスでこの作品を撮っているのでしょう。"死それ自体" を描くことが不可能であるのなら、何を描こうとしているのか。それについて考えようとするのならば、この映画の見方も変わってくるはずです。この映画は退屈などころか、哲学的に考えるための契機が幾つも散りばめられています。それについて以下で考えていきましょう。
![]()
2章 べーザードと穴掘り人カクラマン
![]()
イランの首都テヘランから700㎞離れたシダレア村での葬儀の奇妙な風習を撮影するためにやって来たTVクルーとディレクターのべーザード。通信手段が自分の携帯電話しかなく、しかも電波の状況が悪いので、妻や上司から着信があるたびに、村のはずれの丘までわざわざ車で慌てて移動する様子が度々繰り返される。
その丘で、べーザードは地中から聞こえる歌声の方に向かうと、そこには穴掘り人がいた。べーザードに気付いた穴掘り人は照れて歌うのを止めるが、べーザードはどうせお互いのを姿は見えないのだから、歌を続けるよう催促する ( 1~3. )。それに対して穴掘り人は "僕からは見える ( だから照れて歌えないということ )" と答える ( 4. )。これは何気ないセリフですが、穴の底の人間は暗闇の中にいながらも外の世界が見えている というこの映画の重要な哲学的モチーフにも繋がるものになっています。

べーザードと穴掘り人カクラマンのやり取り ( 5~10. )。
" 何してるんだ? " by べーザード
" 井戸を掘ってる ( もちろん冗談 )" by カクラマン
" 穴だ " by カクラマン
" 何かを埋めるのか? " by べーザード
" 電話線だ ( これも冗談 ( *A ) )" by カクラマン

穴の中にある何かに気付くべーザード。カクラマンにそれを放り投げてもらうと人間の大腿骨だった …… けど驚く様子もなく自分の足の長さと比べてノッポだ … って冗談が出る ( 11~16. )。ここから分かることは、カクラマンが村人の遺体の埋葬のための穴掘りの仕事に従事しているという事。丘の上は村人たちの質素な墓地が幾つもある ( シーン 1. でべーザードの周りに不自然に立てられた無数の石によってそこが墓地であることが示されている ) ので、新しい穴を掘っていたら、誰かが埋葬された穴にぶつかってしまったという訳ですね。

ここで重要なことは、カクラマンの姿が最後まで見えないことです ( 厳密に言うなら、後で土砂崩れにより生き埋めになった穴の中から救出された際、運ばれる姿の足元のみが写るシーンはある )。対話相手の片方の姿が見えないという奇妙な演出。普通の映画ならありえないのですが、これはキアロスタミによってわざと演出されている。
地中の穴が、人間の行き着く先、つまり、"死" を象徴しているとしたら、まだ死なずに穴の中にいる人間 ( カクラマンや彼の恋人、『 桜桃の味 』のバディ、など ) は、死の領域に踏み込み、実存主義的不安の中に落ち込んでいる といえます。彼らの姿を見せない事で、キアロスタミは、人間主体の内奥にある暗闇が死に隣接するものであり、そこに囚われたままでは死にかねない事を示唆している ( 人間の消失という意味で ) のです。この穴の中の人間を外の風景に触れさせる事こそキアロスタミの試みに他ならない のですが、彼はそれをカクラマンの恋人を通じて描き出しているので、考えていきましょう。
( *A )
本当に電話線を埋めていると思う人もいるかもしれませんが、これはべーザードが訪れたカフェの女主人との以下の会話シーンを受けたキアロスタミ流のユーモア。このようにキアロスタミは度々、登場人物のセリフやある場面のモチーフなどを違う場面でさりげなく拾い使用する。それだけ構成や編集に気を配っているという事ですね。

![]()
3章 風が私たちを運んでいく
![]()
べーザードは、カクラマンから聞いて、彼の恋人ゼイナブのもとへ搾りたての牛乳をもらいに行く。彼女もカクラマン同様、暗闇の中にいる。姿は分かっても顔は分からない。

べーザードは彼女にイランの女性詩人 フォルーグ・ファッロフザード ( 1936~1967 ) の詩『 風が私たちを運んでいく 』を聴かせる。この詩こそが映画のタイトルになっている。この詩をすべて朗読させていることから、この映画においていかに特別な意味を持たせているかが分かりますね ( 23~45. )。ただし、邦題は『 風が吹くまま 』であり、ニュアンスの違いがある。細かい違いなのですが、『 風が私たちを運んでいく 』は "私たち" という言葉がある通り、風が人間に課せられた重しを取り外し軽やかに運んでいくというイメージを喚起させる ( 英語の映画タイトルも『 The Wind Will Carry Us 』と原題を踏まえている )。
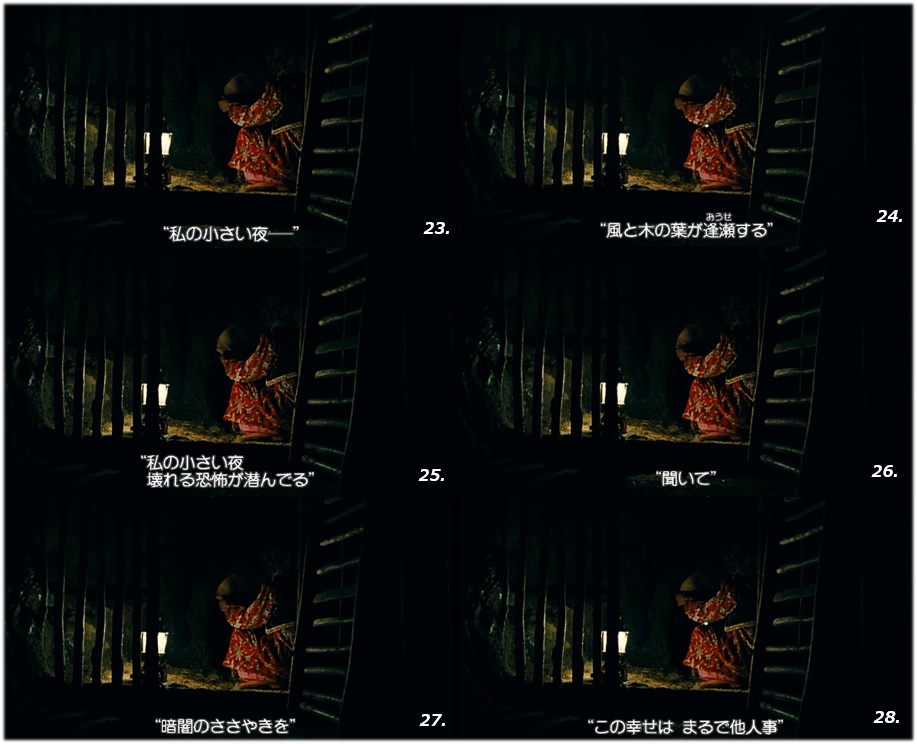
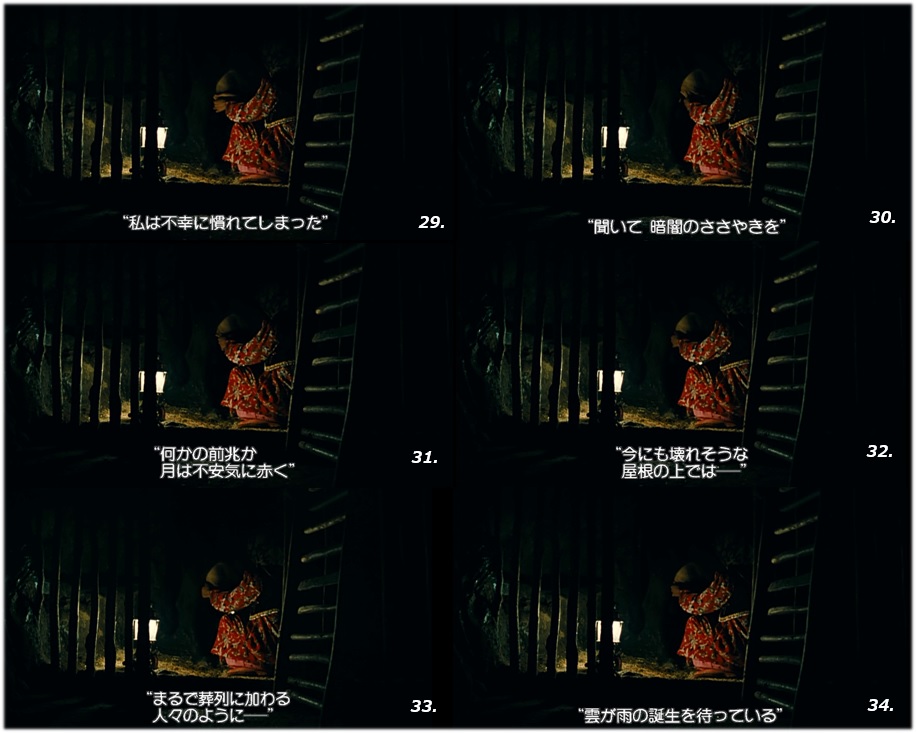
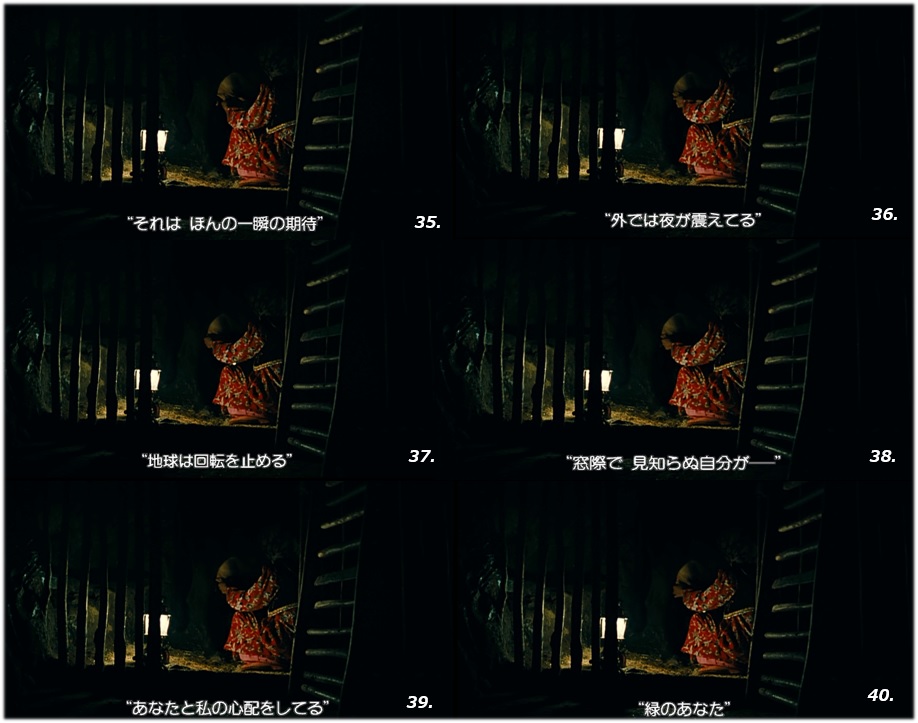
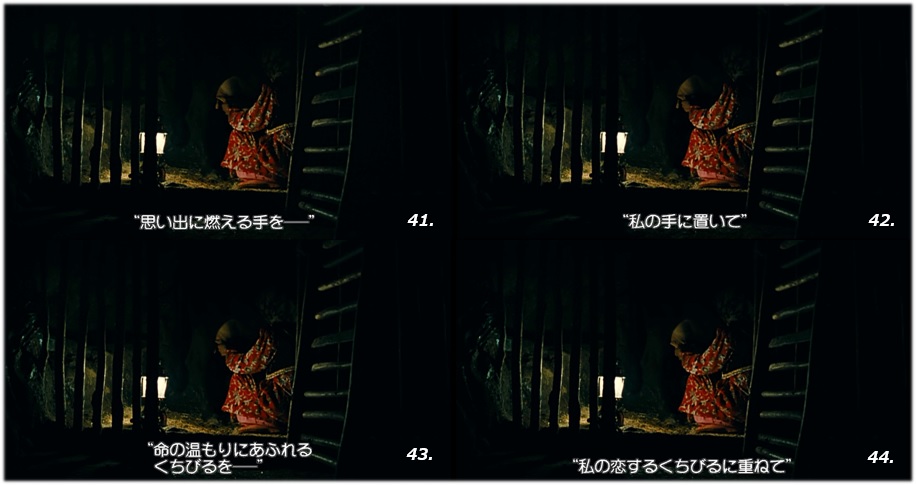

キアロスタミは人目を避けて暗闇で会うことしか出来ないカクラマンとゼイナブを、彼らの制約された不自由な世界から解放してあげたいと考えている。不自由な男女の逢瀬を、風と木の葉、雲と雨、夜と月、地球と緑 …… という具合に、風景世界において隣り合うもの同士を恋人関係に重ね合わせているフォルーグの詩 をどうしようもない人間関係・政治関係からの解放として解釈しているといえるでしょう。人間を実存主義的不安の闇に逃げ込ませるようないびつな制約性を、"風景世界の描写で書き換えよう" とキアロスタミはしている のです。
そして、おそらくこの映画を観たほとんどの人は穴掘り人のカクラマンと暗闇で牛の乳を搾るゼイナブが付き合っていることすら読み取ることが出来ずにスルーしているでしょう。たしかに、そのような直接的描写をキアロスタミは行っていないのですが、注意深く何回か見れば、セリフの隅々から十分に読み取ることが出来るはずです。カクラマンとゼイナブがなぜ暗闇で会い、姿を見せない存在として描かれているかの理由を推測する事も出来ますね。べーザードが牛乳をもらいにカクラマンの家 ( 家というより穴倉なのですが … ) を隣家に尋ねた時、クルド語で対応されて理解できないというちょっとした場面があり、そこからカクラマンがクルド人である事、一緒に住んでいる恋人のゼイナブもクルド人である事が分かるでしょう。
ここでクルド人が国家を持たない少数民族であり、イランやトルコから迫害を受けてきた政治状況を考慮すると、カクラマンとゼイナブが姿を見せない存在として描かれる理由の一端が窺えるというものです。ただし、これを以て、この映画の核心が政治的主張にあると勘違いすべきではないでしょう。それはこの映画の構成要素のひとつでしかないし、そもそもキアロスタミは、モフセン・マフマルバフのように政治的状況をストレートに題材にする映画監督ではありませんからね。
哲学的に考えるならば、彼の牧歌的印象を与える映画には、実存的不安が渦巻く自己意識の肥大を、遠方的な風景描写を媒介にして極小化する "人間の形象化作用" が働いている ( *B )。自己の存在を浸食しかねない肥大化した死に至る自己意識は、風景描写との対比によって、自然の他の要素と共に存在することを思い起こさせる遠方からの形象的な存在として抑制されるのです。
( *B )
人間の形象というキアロスタミの概念については、以下の記事を参照。
![]()
4章 穴から引きあげる …… そして風景になる
![]()
死に至る人間の経験は本人にしか分からないものであり、そこに他の人間が入り込む余地はないでしょう。それが出来るのなら、本人の経験という現象自体が、他人によって容易に書き換えられるという意味で、脆く崩れ去ってしまう。何らかの経験をするのが他人ではなく、自分であると信じる自己意識が簡単に崩壊するのなら、そもそも個人という特殊な圏域自体が成り立たない。つまり、そこに個人はない …… 。
それを念頭に置くと、逆説的な事に、自殺する人間は、自己意識が弱まってそうするのではなく、自己意識が極限にまで肥大化し、周囲に対して鋭敏になり過ぎた結果として、その選択をするという事が分かるでしょう。残念ながら、そこに他人が踏み込むことは出来ないのです。
ここで思い起こすべきは、実存的不安に落ち込んでいる人間が、底を見つめるだけでなく、時折、上を見上げ、外の世界と繋がろうとする素振りを見せる事 です。穴の中からべーザードと会話するカクラマン。暗闇の中でべーザードと会話するゼイナブ。そして『 桜桃の味 』で自殺しようとして穴の中に横たわり、天空の星々を眺めるバディ。
死に至る者は、どれほど闇の中に逃げ込んだとしても、外の世界との繋がりを細い糸で残している。その繋がりは簡単に切れてしまうが、キアロスタミはそれを放っておくことはしない。彼はそういった人たちを助けることを映画で描いているのですが、人道的倫理や道徳観念に依拠してそうするのではありません。
キアロスタミは、誰かを救うというよりは、もっと根本的な出来事、"人の繋がり" について描いているのです。カクラマンやゼイナブのように繋がりが切れそうであるのなら、その細い糸を強く握りしめる。繋がりが十分だと思うのなら、そっと見守る ( べーザードが年取った夫婦の喧嘩を見つめる場面 )。繋がりが弱まったと思うのなら、元に戻そうとする ( 少年を罵ったべーザードが彼と仲直りしようとする場面 )。
キアロスタミは、そのような繋がりを人間の心理的次元を起点にして為される行動として描くのではなく、それがどこででも見受けられる日常の一部として描くことを大切にしている。それは繋がりを認識することが大事というよりは、繋がりという糸を時には強く、時には優しく握るというように、"人と人との間に横たわる何か" に触れることの感覚を説くもの です。それを言葉で説明するのではなく、風景として描き出すところにキアロスタミの特徴がある ( そのような感覚を教えてくれるのが自然です。『 桜桃の味 』、『 風が私たちを運んでくれる 』といったタイトルからも分かるはず )。人間をクローズアップしてそこに焦点を絞るやり方が必ずしも人間的であるわけではありません ( むしろサスペンスやホラー映画で見受けられるようにそれは人間に中にある非人間的なものの恐怖を煽る )。
最も人間的なものである "繋がり" を風景に直結させて描き出す ところにキアロスタミの凄みはあります ( それは彼によるフォルーグの詩の解釈にも繋がっていく )。彼は決して漠然と牧歌的映画を描いたのではなく、人間的なものの観察、人間関係、人間を取り巻く状況、などの幾つもの要素を下積みにして作品を創っていたのですね。そういった事を踏まえると、キアロスタミの作品はもっと味わい深くなるでしょう〈 終 〉。

![]()