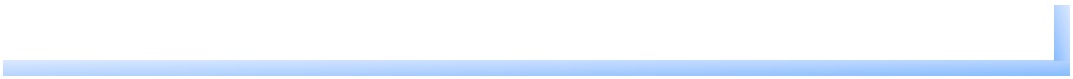![]()

![]() 上記 ( 前回 ) の記事からの続き。
上記 ( 前回 ) の記事からの続き。
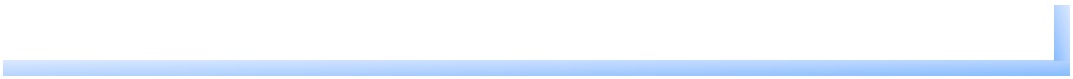
シークエンス 26.
クネゴンダを再び探すために老人たちばかりが集まる村に来たカンディードとカカンボ。ここにいる老人たちは "フラワーチルドレンという平和と愛と非暴力の集団" だと説明されていますが、もちろんこれは1960代後半から1970年代にかけてアメリカでのフラワームーブメントを担ったヒッピーたちの事。ここでは、社会的束縛に抵抗する事に熱中した若者であったヒッピー達の成れの果ての姿を描いている。
ただし、これはヒッピー達への批判というよりは、社会的抵抗を求め自由を謳歌する若者でさえも、いずれ老いていくという誰にも共通する人間の経験 を表していると考えるべきでしょう。
村人はクネゴンダの居場所ならダルヴィーシュに聞けとカンディードに言う。ダルヴィーシュとはイスラム神秘主義 ( スーフィー ) の修道僧の事。原作でもダルヴィーシュは出てくるのですが、映画ではヒッピー達の村にイスラム神秘主義の修道僧がいるという奇妙な状況になってます ( 笑 )。

![]()
シークエンス 27.
なぜかヒッピーの村にいるクネゴンダを見つけるカカンボ。ダルヴィーシュに聞けと言った村人のアドバイスをまるっきり無視する流れ。一体何だったの。クネゴンダの姿を確認したカンディードは一瞬目を潤ませるのですが、すぐに彼女が老けてしまっている事に気付きます。

![]()
シークエンス 28.
そこに突然現れるかつての知り合い達。TVディレクターだったパングロスも元の姿に戻っている。男爵、奥方もいる。そしてカンディードは、ダルヴィーシュを訪ね、哲学問答を始める。
"人間と言う妙な動物はなぜ存在するんです?"
"この世は邪悪すぎます" by カンディード
"善悪を気にするなどお前のやるべき事か" by ダルヴィーシュ
カンディードの問いに対してダルヴィーシュは明確な答えを与えられず期待はずれなのですが、彼の発言は映画の結末 ( 原作も含めて ) に対する哲学的解釈を行う上での基本的な伏線となっているといえるでしょう。それについては後で考えていきますね。

![]()
シークエンス 29.
"なぜ若さは すぐ消える?" by カンディード

![]()
シークエンス 30.
目の前の川を見ながら、最善説を反芻するカンディード。だがここで彼は最善説から、ある種の運命論へ移行しつつある事が分かる。
"流れがなければシンボルは反対の岸に流れ着くが 結局 若者たちが またそれを川に投げる"
"運命だよ 逃れようがない" by カンディード

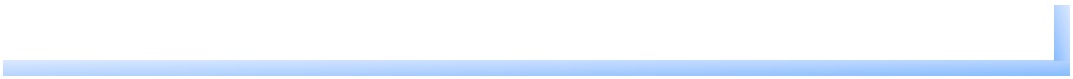
4章 結末の解釈
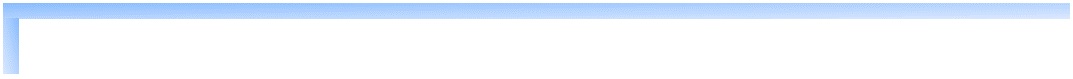
さて映画の結末について考える前に、原作の結末に触れておく必要があるでしょう、映画との差異を浮かび上がらせるためにも。
世界各地を放浪した末にパングロスは仲間達と共に、小さな畑を耕すという日常に没頭していきます。
"ぼくにわかっていることは ひとは自分の畑を耕さなければならない、ということ" by カンディード
"人間がエデンの園においてもらったのは、聖書にもあるとおり、そこを耕すため、つまり、労働をするためなのです" by パングロス
"議論とかするひまがあったら働きましょう。それのみが人生を我慢できるものにする唯一の方法なのです" by マルチン
このように、原作における結末である第30章は、最善説的な哲学議論から 労働 への移行が描かれています。この部分は、カンディードの "ひとは自分の畑を耕さなければならない" というセリフと共に、ヴォルテールに関心のある人達にとって、常に解釈の対象となっていました、まるでカンディードの言葉に何らかの哲学が含まれているかのように。たとえば、抽象的に解釈するならば、答えの出ない哲学議論のような他の領野の中で迷走するよりは、自分の手が届く日々の生活の営みに集中する事の方が有意義な人生の過ごし方なのではないか、という具合に。
しかし、カンディードとダルヴィーシュの哲学問答で示されていたのが哲学的思考の停止に他ならないとするならば、カンディードのセリフに含まれていたのは、哲学的なものものではなく、それどころか、哲学理論からの撤退以外の何物でもない のは明らかでしょう。つまり、カンディードのセリフは人生論的には有効でも、理論的には後退している。( *8 ) で記したように、それはヴォルテール自身が認める所でしょう。
そんな原作に対して、ヤコペッティの映画のラストは理論的なものについて考える可能性を残しているという意味で、ヴォルテールの原作以上に興味深いものになっています。
![]()
シークエンス 31.
"ダメだ 行くな 痛い目に遭うだけだ" by 川の対岸に自分の姿を見つけたカンディード
"痛い目に遭いたいのさ"
"最初から全部また経験するんだろ" by 去り際に冷静なセリフを残すカカンボ

このラストによって、ヤコペッティはヴォルテールの原作の中では最善説の裏で漠然とした形でしか現れてなかった経験論を主体に帰す形で浮かび上がらせ、さらにその帰結を提示したのでした。つまり、最善説に反対するにせよ、賛成するにせよ、それ以前に、そこにはまず 何かを経験する主体 が先立つのであり、その 経験という現象 は当然ではなく、主体にとっての特別な出来事であるという哲学理論が現れるのです。
このことはヴォルテールが放棄した理論的に考えるという知識の仕事は、もはや止められない事を意味します。パングロスはエデンの園に言及しましたが、アダムはそこで知恵の樹の実を食べたが故に、イヴと共に追放されたのでした。それはどういう事なのか。
何かを知ることは罪なのではなく、何かを知ろうとする事は止められないが故に、どうにもならない事なのです。知る事とは、喜びや楽しみだけではない、負の側面を知る事も含むので自らの楽園から出て行くことでもあるのですね。ならば、私達は知る事が出来るのに、知らないままに安住する態度こそ、さらなる罪である事を哲学的に理解する必要があるでしょう。知らないままでいる態度とは、詰まる所、知る事が出来るのにそれを拒否するという最悪の否定性に留まる事 をも意味するのです。
シークエンス31. において、ヤコペッティは経験する主体にさらに捻りを加えています。主体が経験した事を再び経験するという永劫回帰的モチーフを導入している のです。この時、主体には何が起き、哲学的にどう考えなければならないかは大きなテーマとなるので機会があれば、その時に論じましょう。いずれにせよ、ヤコペッティの『 大残酷 』は、ヴォルテールのカンディードが放棄した哲学理論的に考え続ける事の可能性と、映画それ自体を娯楽として楽しむ可能性を内包しているといえるでしょう〈 終 〉。
![]()
〈 関連記事 〉