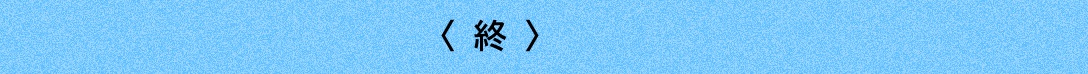映画 『 草原の実験 』 ( 露 : Испытание / 英 : Test )
監督 アレクサンドル・コット ( 露 : Александр Котт / 英 : Alexander Kott、born : 1973~ )
公開 2014年
出演
エレナ・アン ( Elena An : 1998~ ) ディナ / トルガットの娘
カリム・パカチャコフ ( Karim Pakachakov ) トルガット / ディナの父親
ダニラ・ラッソマヒーン ( Danila Rassomakhin ) マックス / ディナの恋人・金髪
ナリンマン・べグブラトフ・アレシェフ ( Narinman Bekbulatov-Areshev ) カイシン / ディナの元恋人

第1章 父と娘

▨ カザフスタンの草原でトルガットは娘のディナと二人で生活している ( 1 )。 見渡す限り草原が続く大地。 映画の冒頭では各爆破実験で全てが吹き飛ぶ大地の様子が描写される。 爆風の中に舞い落ちる綿。 そして場面 ( 7 ) のディナが手を置く綿からも分かるようにトルガットは綿花の栽培を始めとする農業に従事している事が分かる。 トルガットの前に着陸する飛行機 ( 2~3 )。 家の中から様子を伺うディナ ( 4 )。 その飛行機の操縦に興奮を抑えきれないトルガットは子供のように無邪気に喜んでいる ( 5~6 )。 飛行機を操縦させてくれた馴染みの軍人と握手するトルガットと傍のディナ ( 7~8 )。 トルガットは第二次世界大戦中にカザフスタンの空軍パイロットだったが、 久しぶりの運転に興奮を隠しきれなかった。 何の変哲もない日常の中の非日常。 それはトルガットに戦時中を思い起こさせるものであり、 それはおそらく彼の中で、 戦い続ける事で自分を独りの男として成長させた人生の大切な時間だったといえるものです。 しかし、 このささやかな男の誇り、 そして恋人と共に生きようとする娘のディナの人生も、核爆破と共に粉々に打ち砕かれてしまう …… 。

▨ ディナには恋人カイシンがいる。 彼女と同じくカザフスタンの男性である彼は、 ディナの父親程、 家父長的人間ではない ( ディナは仕事から帰ってきた父親の靴や服を脱がして上げている ) が、 馬に乗ったままディナから水をもらい残した水を岩にかけ捨てるという場面 ( この場面は2回繰り返される ) から示されるように、 素朴ではあるものの、 ある種の男性優位を象徴する人間となっている ( 9~10 )。 その一方でディナはノートに柄物や木の葉などによるコラージュ作品をつくり、 芸術的な内面世界を垣間見させる。 ここには男性社会には従属しない彼女の主体性が秘かに表されている ( 11~14 )。 そして、 そのような日常の人間関係の終焉を予感させるかのように最後の一枚の木の葉が落ちていく ( 15~16 )。


第2章 ディナとマックス

▨ ディナの前に現れるマックス。 草原を運転中に水をもらいに来た彼との出会いはカイシンの場合とは違う "恋愛" の始まりだった ( 17 )。 カイシンとの関係が男女の主従関係に基づいているとするなら、 マックスの場合は、 対等な人間関係であり、 それは水のやりとりを始め、 カメラを撮るマックス、 そこに被写体として収まるディナ、 等の水平的構図で示されている ( 18~22 )。 マックスの西欧的容貌自体がカザフスタンの 地縁共同体 の外部性を象徴していて、 その外部からの訪問者はディナの外に飛び出したいという 脱共同体的欲望 に応えるかのようにしてディナに会いに来た といえるでしょう。

▨ 夜中にディナに再び会いに来たマックス。 昼間に撮った写真を投影機でディナの家の壁に映しだす。 ディナの顔のクローズアップ ( *1 )。 台詞が全くないこの作品 ( *2 ) では、 マックスの投影行為が、 ディナへの告白行為の代わりになっている ( 23~28 )。 見つめ合う二人 ( 29~30 )。

▨ ディナを抱きしめるカイシン。 その様子を窓の外から見てしまうマックス ( 31~34 )。 二人は恋敵として戦うが、 あきれたディナに頭から水をぶっかけられてしまう ( 35~36 )。

( *1 ) 映画史においては女性の顔のクローズアップは、 謎めいた 女性的なるもの への愛着や畏怖などの心理的複合物 ( コンプレックス ) を抱く男性の投影化として用いられてきた。 イングマール・ベルイマンの 『 仮面 / ペルソナ ( 1967 ) 』 、 クリス・マルケルの 『 ラ・ジュテ ( 1962 ) 』 など。
( *2 ) アレクサンドル・コットは台詞のない作品として新藤兼人の 『 裸の島 ( 1960 ) 』 を参照している。 瀬戸内海の小島 ( 宿禰島 ) における地縁共同体の中で生きていく人間の姿を描いている。
そして新藤兼人の作品には、 アメリカの水爆実験で被爆したマグロ漁船の船員たちを描いた 『 第五福竜丸 ( 1959 ) 』、 広島の原爆投下を描いた 『 原爆の子 ( 1952 ) 』 などがある。 アレクサンドル・コットもおそらく参照しているでしょう。

第3章 トルガットの死

▨ 朝方に家の扉をこじ開けようとする誰かにディナは銃を身構えて待つ ( 36 )。 その正体は父親だった。 トルガットは核実験場から被爆物質を物珍しさから持ち帰った為、 ソ連軍から連行されていた。 庭にある枯れた木の根元とトルガットの頭頂部が重ね合わされ、 まるで木に水を注いでいるように見える ( 40~43 )。 しかし、 この注ぎは生命回復の為ではない。 被曝により死期が近いことを理解したトルガットは、 死に際して自分の身を水で清めてもらっている。

▨ 死に際して正装するトルガット。 この世での最後の時まで己の誇りを失うまいとする姿勢が描かれる ( 43~46 )。 枯れた庭木の横で日の出を見ながら死に絶える ( 47~49 )。 埋葬されるトルガット ( 50~51 )。 しかし、 このようなトルガットの矜持はラストで粉砕されてしまう、 彼の死んだあとであっても …… 。


第4章 核爆発と人間存在

▨ トルガットの亡き後、 仲睦まじく暮らすディナとマックス ( 52~54 )。 そんな彼らの目に見える範囲で核爆破実験が起きる ( 55~59 )。

▨ 核爆破を前にして死の覚悟をするディナとマックス ( 60~63 )。 爆風の衝撃波は地表をひび割らせながら拡がっていく。 家は吹き飛び、 埋葬されたトルガットの遺体は引きちぎられる程の衝撃で掘り起こされる ( 64~65 )。 ディアたちの人間関係は一瞬にして爆風の中で粉砕された肉片へと "無化" される。 死んだ後でさえも、 その "存在" は徹底的に崩壊させられてしまう。 つい先程まで人間が存在したという事実でさえもが、木っ端微塵の物的断片としてしか省みられなくなるというこの残酷さ …… 。


第5章 このラストをどう解釈すべきか

▨ この帰結をどう考えるべきなのか。 もちろん、 核実験においては何も知らされずに被曝した人々の経験を通じて核の恐ろしさを後世に伝えていくというヒューマニスティックな教訓が大事なのは言うまでもありません。 しかし、 それのみでは映画作品としては余りにも紋切型で核の恐ろしさを伝えるドキュメンタリーに準ずるものでしかなくなってしまう。
▨ ここで引き合いに出すべきは、 この作品が明らかに参照していると思われるアンドレイ・タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 です ( *3 )。 『 サクリファイス 』 の作品背景には核戦争への恐れや不安があり、 平和への希求が暗示されているとも "一般的に" 言われますね。 しかし、 その一般的解釈は漠然としたイメージでしかなく、 深く考えられたものではありません。 それは タルコフスキーの作品自体が無垢な聖性を帯びた芸術的なものと誤解されている 事から来ているといえるものなのです。
▨ もちろん、 このような誤解は、 自分の作品を芸術的なものとして持ち上げるタルコフスキー自身の言葉が原因なのですが、 これは、 自分の作品を説明しようとする映画監督の言葉程、 作品を説明出来ないものはない という教訓のよい例でしょう ( *4 )。 言葉で上手く説明出来るのなら、 映像化にこだわる必然性はなくなってしまうという訳なのですが、 ここには言語的創造の代補物としての映像的創造が時として言語による解釈を斥けてしまう否定的論理として出現している事が含まれている。 だからタルコフスキーが自分作品における映像を "詩的芸術" や "精神性" という言葉で表す時、 彼が〈 言葉 〉というものに対して魅了されつつも、 映像を説明する代補的なものという使い方しか出来ないアンビバレントな反目的関心 を露にしている事に気付かなければなりません ( *5 )。 実際、 彼の著作物を読んでも作品の解釈を深めてくれる決定的なものはないのです、 彼が芸術的観念に囚われているという紋切型が繰り返される以外は。
▨ 彼の真の恐るべきところは、 ひとつの家庭、 ひとりの人間、 ひとりの男、 の 狂気 が全人類の滅亡の危機 ( 核の脅威など ) と対峙的に、 いや、 それ以上の 出来事 として映画内構造化される事で、 人類の危機的状況を強度的に圧倒するという倒錯的かつ暴力的な人間性回復 を描く事なのです。 人間の狂気自体が人間存在の尊厳を回復させるという暴力的聖性 こそが彼の作品の無意識的秘密である事に気付けば ( ラース・フォン・トリアーはそれに気付いている )、 詩的芸術などというタルコフスキー自身の言葉に従っていては何の作品理解も得られないのが分かるでしょう。
▨ 『 サクリファイス 』 におけるそのようなひとりの人間のトラウマ経験 ( 家庭内人間関係における狂気の出現 ) と人類の歴史における普遍的トラウマ ( 戦争や核の脅威 ) の 両極的並置構造 は 『 草原の実験 』 においても引き継がれています。 ただし 『 草原の実験 』 における人間関係は核の脅威を心理的に転覆させるようなタルコフスキー的狂気を生み出さず、 核の脅威による心理的圧迫に最初から従属し、 最後には滅ぼされるという 崩壊主体 としての人間の従属的運命が描かれるのみです。 そう考えると、 『 草原の実験 』 は残酷なラスト以前のありふれた人間関係の描写が、 束の間の幸せなどではなく、 核の脅威という人類的トラウマの恐るべき吸引力に呑み込まれる運命への序章になっているという意味で、 救いがないといえるでしょう〈 終 〉。
( *3 ) タルコフスキーの 『 サクリファイス 』 については以下の記事を参照
( *4 ) 例えば、タルコフスキーは 『 映像のポエジア 』 の中で 「 サクリファイス 」 について次のように言う。
現代人は分かれ道に立っている。かれらの前にはジレンマが立ちはだかっている。新しいテクノロジーの揺るぎない歩みと、物質的価値のさらなる蓄積に頼って、盲目的な消費者の存在を続けるべきなのか、あるいは、結局は、個人だけでなく、社会のためにも、救いの現実になりうるかもしれない精神的な責任への道を探求し、見出すべきなのか。つまり〈 神 〉へ戻るべきなのか。人間自身がこの問題を解かなくてはならない。人だけが正常な精神的生活を見出すことができるのだ。この解決こそが社会にたいする責任への第一歩となりうるのである。この一歩は犠牲、つまり自己犠牲にかんするキリスト教的な観念なのである。
『 映像のポエジア 』アンドレイ・タルコフスキー / 著 鴻 英良 / 訳 ちくま学芸文庫 ( 2022 ) p.346
しかし、 実際には作品において、 彼の言う 精神性 は、 主人公アレクサンデルのトラウマによる性的不能とその克服、 そしてその失敗、 という具合に猥褻性や狂気といった 猥雑な物質性 との両極構造における 暴力的拮抗関係 において立ち現れる。 つまり、 タルコフスキーは自身の作品の 創造的暴力性 については口にする事がないのに注意しなければならないのです。
( *5 ) タルコフスキーの 言葉への希求 がヨハネ福音書を通じて示されている事こそが 『 サクリファイス 』 に込められた秘かなテーマだった事にほとんどの人は気付かない …… 。 この点については ( *3 ) で記した記事を参照。