![]()
![]()
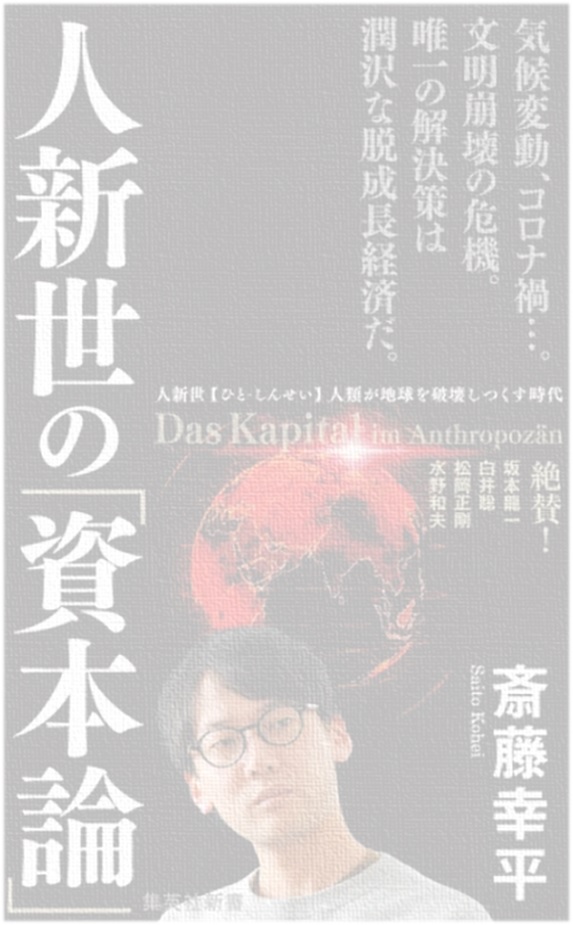
著者 : 斎藤幸平
発行所 : 集英社
2020年 9月 22日 第一刷発行
![]()

![]() CHAPTER1 賞賛でもなく、シニカルな批判でもなく ……
CHAPTER1 賞賛でもなく、シニカルな批判でもなく ……
![]()
![]() 1. 世間で話題の斎藤幸平の『 人新世の「 資本論 」』に対する感想や批評の多く ( Amazon のレビューなど ) がいかにつまらないことか。それは読者が彼の思想を理解していないとか、あるいは "真正の" マルクスの思想を彼に対して対峙させるべきだ、などといういずれの態度にも問題があるという事を言いたいのではありません。そうではなく、賞賛であれ批判であれ、本書を読んでその程度の感想しか持ち得なかったのか、と思わせるものが溢れているという事です。本当に何かを読み取って自分なりに考えたのだろうか、たんに字面を目で追った結果としての印象を語っただけなのではないか、と思わせる多くの感想文は "何かを読み解くという思考行為" の手前で多くの人が留まっている現象が新書の普及と共に起こっている事を示しているのでしょう。
1. 世間で話題の斎藤幸平の『 人新世の「 資本論 」』に対する感想や批評の多く ( Amazon のレビューなど ) がいかにつまらないことか。それは読者が彼の思想を理解していないとか、あるいは "真正の" マルクスの思想を彼に対して対峙させるべきだ、などといういずれの態度にも問題があるという事を言いたいのではありません。そうではなく、賞賛であれ批判であれ、本書を読んでその程度の感想しか持ち得なかったのか、と思わせるものが溢れているという事です。本当に何かを読み取って自分なりに考えたのだろうか、たんに字面を目で追った結果としての印象を語っただけなのではないか、と思わせる多くの感想文は "何かを読み解くという思考行為" の手前で多くの人が留まっている現象が新書の普及と共に起こっている事を示しているのでしょう。
![]() 2. ここでは、本書を読んでそこに内在する哲学原理を幾つか抽出し、それについて考えてみます。本書の理論的限界に対する批判として為すのではなく、本書を読む者が、自らの思考の限界とそこからの展開を促す。そうする事によって本書の内容を自分の中で継続的に考え、変化させていく事が出来るでしょう。そういう作業をせずに本書の理論的欠点を著者に短絡的に帰す事しかしないのであれば、その人は自分の時間 ( 読書の ) を無駄に使ったという間抜けな告白をしているに過ぎないのです。
2. ここでは、本書を読んでそこに内在する哲学原理を幾つか抽出し、それについて考えてみます。本書の理論的限界に対する批判として為すのではなく、本書を読む者が、自らの思考の限界とそこからの展開を促す。そうする事によって本書の内容を自分の中で継続的に考え、変化させていく事が出来るでしょう。そういう作業をせずに本書の理論的欠点を著者に短絡的に帰す事しかしないのであれば、その人は自分の時間 ( 読書の ) を無駄に使ったという間抜けな告白をしているに過ぎないのです。

![]() CHAPTER2 権力闘争から物の政治へ
CHAPTER2 権力闘争から物の政治へ
![]()
![]() 1. 本書を読んで、気候変動などの環境問題がマルクス主義の文脈で語れられる事の必然性について疑問に思った人もいるでしょう。著者はマルクスの研究ノートから晩期マルクスにおける物質代謝論に注目してマルクス主義的エコロジー論を考えようとする。資本主義と自然環境のとの亀裂的関係性から、社会主義の方へと赴くマルクスの埋もれた思想は確かに重視されるべきなのですが、ここには目新しさと同時に未だ以前と変わらない枠組みが残っている。つまり、社会規模であれ、地球規模であれ、疎外された人間性が "集団的主体" として常に回帰してくる という変わらない理論的構図がある。労働者階級、地球上における人間という動物集団など。
1. 本書を読んで、気候変動などの環境問題がマルクス主義の文脈で語れられる事の必然性について疑問に思った人もいるでしょう。著者はマルクスの研究ノートから晩期マルクスにおける物質代謝論に注目してマルクス主義的エコロジー論を考えようとする。資本主義と自然環境のとの亀裂的関係性から、社会主義の方へと赴くマルクスの埋もれた思想は確かに重視されるべきなのですが、ここには目新しさと同時に未だ以前と変わらない枠組みが残っている。つまり、社会規模であれ、地球規模であれ、疎外された人間性が "集団的主体" として常に回帰してくる という変わらない理論的構図がある。労働者階級、地球上における人間という動物集団など。
![]() 2. これらの集団的主体性は常に、権力に対する対抗的勢力として意義があると無批判的に受け入れられてきた ( このような階級構造や上・下部構造などマルクス主義的カテゴリーの理論的有効性については昔から批判もある ) のですが、このような集団的主体性が果たして民主主義社会を変革する真に革命的勢力なのかどうかは冷静に考える必要がある という事です ( *1 )。例えば労働者の組合運動、権利の主張、などはマルクスが夢想したように資本家を打倒す事を目指しているからそうするのではなく、労働集団としての自分たちの生活を守るために行われている。資本家がいなくなってしまっては、誰も自分たちの給料を払ってくれず、生活が成り立たない事が分かっているのですね。集団は "何か" を変革するのではなく自らの集団性を維持し守るために動く のであれば、社会変革とは一体何なのか考え直さなければならないでしょう。
2. これらの集団的主体性は常に、権力に対する対抗的勢力として意義があると無批判的に受け入れられてきた ( このような階級構造や上・下部構造などマルクス主義的カテゴリーの理論的有効性については昔から批判もある ) のですが、このような集団的主体性が果たして民主主義社会を変革する真に革命的勢力なのかどうかは冷静に考える必要がある という事です ( *1 )。例えば労働者の組合運動、権利の主張、などはマルクスが夢想したように資本家を打倒す事を目指しているからそうするのではなく、労働集団としての自分たちの生活を守るために行われている。資本家がいなくなってしまっては、誰も自分たちの給料を払ってくれず、生活が成り立たない事が分かっているのですね。集団は "何か" を変革するのではなく自らの集団性を維持し守るために動く のであれば、社会変革とは一体何なのか考え直さなければならないでしょう。
![]() 3. ここで考えるべきは、"集団性" それ自体が権力に対抗しうると同時に、権力によって囲い込まれ停滞させられている未だ集団性に至らないままでいる "大多数" でもある という事です。大多数 ( マルチチュード ) …… かつて アントニオ・ネグリ と マイケル・ハート によって提示され注目を集めたこの主体概念が権力を打破するという考えは、民主主義国家において果たしてどれ程説得力を持つのか。民主国家において日常の中に回収され収束していくデモが本来の力を発揮するのは、不安定な政情国家における状況打開期においてである と認めなければ、いつまでもマルクス主義的カテゴリー概念に何の注意も払わずにすがりつくだけになってしまう。
3. ここで考えるべきは、"集団性" それ自体が権力に対抗しうると同時に、権力によって囲い込まれ停滞させられている未だ集団性に至らないままでいる "大多数" でもある という事です。大多数 ( マルチチュード ) …… かつて アントニオ・ネグリ と マイケル・ハート によって提示され注目を集めたこの主体概念が権力を打破するという考えは、民主主義国家において果たしてどれ程説得力を持つのか。民主国家において日常の中に回収され収束していくデモが本来の力を発揮するのは、不安定な政情国家における状況打開期においてである と認めなければ、いつまでもマルクス主義的カテゴリー概念に何の注意も払わずにすがりつくだけになってしまう。
![]() 4. ネグリ=ハートの思想が根本的に間違っているかもしれないのは、集団的主体をマルチチュードのように定義づけする事自体が、革命の潜勢力を解き放つかのような印象を与えている という事です。集団的主体の定義付けが、集団的主体、この場合、マルチチュード "である" という存在論的身分の保証として機能し、もうそれだけで主体の欲望を満足させてしまう。マルチチュードであれ、エチエンヌ・バリバールの市民主体であれ、何らかの抽象的主体が政治行動を起こすという叙述の仕方自体が既に、実際の具体的行動ではなく、権力関係の話をしているに過ぎない事 に気が付かなければならないのです。
4. ネグリ=ハートの思想が根本的に間違っているかもしれないのは、集団的主体をマルチチュードのように定義づけする事自体が、革命の潜勢力を解き放つかのような印象を与えている という事です。集団的主体の定義付けが、集団的主体、この場合、マルチチュード "である" という存在論的身分の保証として機能し、もうそれだけで主体の欲望を満足させてしまう。マルチチュードであれ、エチエンヌ・バリバールの市民主体であれ、何らかの抽象的主体が政治行動を起こすという叙述の仕方自体が既に、実際の具体的行動ではなく、権力関係の話をしているに過ぎない事 に気が付かなければならないのです。
![]() 5. 実際の具体的政治空間を切り開くには、何に関心を持ち、それについてどう考え、どう行動するかという市民による "抽象化作業" が必要になるのですが、それは各国家、各市、各町村、各時期、各人間、等が絡み合う諸関係性に応じて異なったものとして多数出現するはずなのに、連帯性を義務付けるかのようなカテゴリー的名称化による集団的主体性の強調は、集団における多様なアプローチを阻害しかねない抑圧的なものなる危険性があるといえるでしょう ( 集団内における権力闘争の発生など )。
5. 実際の具体的政治空間を切り開くには、何に関心を持ち、それについてどう考え、どう行動するかという市民による "抽象化作業" が必要になるのですが、それは各国家、各市、各町村、各時期、各人間、等が絡み合う諸関係性に応じて異なったものとして多数出現するはずなのに、連帯性を義務付けるかのようなカテゴリー的名称化による集団的主体性の強調は、集団における多様なアプローチを阻害しかねない抑圧的なものなる危険性があるといえるでしょう ( 集団内における権力闘争の発生など )。
![]() 6. そういう点からすると、本書における斎藤幸平は安易な集団的主体性の概念に頼らない代わりに、環境問題と資本主義の結びつきを問題視する。ここにはたんなるマルクス主義的グリーンディールだとは決めつけられない思想的偏奇があります。それは斎藤幸平自身も意識的に説明出来ていないのですが、それまでのマルクス主義理論は共産主義という名の下での権力闘争 ( だからそこでは常に 集団的主体の地位 が問題になる ) に最終的に収斂されていたと大雑把に言えるのに対して、彼は "権力闘争" からより "物の現実性" へと "政治の場" を移行させる。派閥などの政治家の関係性が力を占める舞台劇ではなく、現実に起こった、起こるであろう現実の諸問題を "哲学的・行政的に" 解決する事の重要性が多くの市民によって共有される "物の政治化" こそが大切だ、という無意識的メッセージを送っているのです ( もちろん、これは "読解" であり、斎藤の意図に反しているともいえる )。
6. そういう点からすると、本書における斎藤幸平は安易な集団的主体性の概念に頼らない代わりに、環境問題と資本主義の結びつきを問題視する。ここにはたんなるマルクス主義的グリーンディールだとは決めつけられない思想的偏奇があります。それは斎藤幸平自身も意識的に説明出来ていないのですが、それまでのマルクス主義理論は共産主義という名の下での権力闘争 ( だからそこでは常に 集団的主体の地位 が問題になる ) に最終的に収斂されていたと大雑把に言えるのに対して、彼は "権力闘争" からより "物の現実性" へと "政治の場" を移行させる。派閥などの政治家の関係性が力を占める舞台劇ではなく、現実に起こった、起こるであろう現実の諸問題を "哲学的・行政的に" 解決する事の重要性が多くの市民によって共有される "物の政治化" こそが大切だ、という無意識的メッセージを送っているのです ( もちろん、これは "読解" であり、斎藤の意図に反しているともいえる )。
![]() 7. この権力闘争から物の政治への移行において重要な役割を果たすのが、環境問題という "物の現実性" です。権力闘争的政治において現実の諸問題は、政治に関わる者の人間関係と絡み合う相関的な事案としてその現実性が差し引かれる側面が強かったのですが、環境問題は、権力闘争を重視する政治家が、現実の諸問題が私たち市民をいかに強く規定し圧迫させているかを軽視している事を露にする "物" なのです ( *2 )。
7. この権力闘争から物の政治への移行において重要な役割を果たすのが、環境問題という "物の現実性" です。権力闘争的政治において現実の諸問題は、政治に関わる者の人間関係と絡み合う相関的な事案としてその現実性が差し引かれる側面が強かったのですが、環境問題は、権力闘争を重視する政治家が、現実の諸問題が私たち市民をいかに強く規定し圧迫させているかを軽視している事を露にする "物" なのです ( *2 )。
![]() ( *1 ) 民主主義が普及・安定していない国家、独裁政権・軍事政権・共産政権、などの支配形態が力を有する国家において、集団的抵抗力が民主主義への道を切り開く契機となる事はあっても、民主主義的安定がある程度普及した国家においては、デモなどの集団行動が瞬間的沸騰であり すぐに日常の中に回収されてしまう事の意味 を今一度考えなければならないという事です。
( *1 ) 民主主義が普及・安定していない国家、独裁政権・軍事政権・共産政権、などの支配形態が力を有する国家において、集団的抵抗力が民主主義への道を切り開く契機となる事はあっても、民主主義的安定がある程度普及した国家においては、デモなどの集団行動が瞬間的沸騰であり すぐに日常の中に回収されてしまう事の意味 を今一度考えなければならないという事です。
![]() ( *2 ) このような "物の政治化" は "物の思想化" との照応関係を見出す事も出来る。物の思想化とは、近年注目されるようになった新実在論に代表されように物の実在それ自体が思考の圏域の内に占める意味が見直されるというものです。このことの哲学的意味は他所に譲るとして、その哲学における政治的意味は、哲学研究が専門家同士の内部で該当の哲学者を詳細化するのに傾き過ぎる事 ( もちろん全てがそうではない ) に対し、個別の哲学者を越えて哲学本来の思考を展開させていく "行為" が改めて促進された という事です。例えば、グレアム・ハーマンはハイデガーの四方界をヒントにして四方対象の概念を構築させていったのですが、ハイデガー研究者たちの多くはそれを冷ややかな目で見て黙殺している。これはハイデガー研究者がアカデミズムという無自覚な専門的権力性に囚われたまま ( 他の専門家も同じように ) で、"物" に対してどのようにアプローチすべきか、私たちに対して立ち塞がる "物自体へのアクセス不可能性" の現実的意味をどう考えるか、という哲学本来の "普遍的なもの" へ向かう力を失っている事の現れだといえるでしょう。
( *2 ) このような "物の政治化" は "物の思想化" との照応関係を見出す事も出来る。物の思想化とは、近年注目されるようになった新実在論に代表されように物の実在それ自体が思考の圏域の内に占める意味が見直されるというものです。このことの哲学的意味は他所に譲るとして、その哲学における政治的意味は、哲学研究が専門家同士の内部で該当の哲学者を詳細化するのに傾き過ぎる事 ( もちろん全てがそうではない ) に対し、個別の哲学者を越えて哲学本来の思考を展開させていく "行為" が改めて促進された という事です。例えば、グレアム・ハーマンはハイデガーの四方界をヒントにして四方対象の概念を構築させていったのですが、ハイデガー研究者たちの多くはそれを冷ややかな目で見て黙殺している。これはハイデガー研究者がアカデミズムという無自覚な専門的権力性に囚われたまま ( 他の専門家も同じように ) で、"物" に対してどのようにアプローチすべきか、私たちに対して立ち塞がる "物自体へのアクセス不可能性" の現実的意味をどう考えるか、という哲学本来の "普遍的なもの" へ向かう力を失っている事の現れだといえるでしょう。

![]() CHAPTER3 環境問題という物、資本主義という物 ……
CHAPTER3 環境問題という物、資本主義という物 ……
![]()
![]() 1. しかし、問題なのは、"物としての環境問題" 以前の、"物としての資本主義" です。環境問題が政治を権力闘争から現実的解決問題へと移行させるのは良いとしても、環境問題が極めて資本主義的な問題である事です。ここで資本主義的問題であるというのは、資本主義が惹き起こす環境汚染や気候変動などの危機的事象であるという事 ( それについては本書で述べられているので参照 ) ではなく、資本主義によって惹き起こされる環境問題に取り組む私たちの行動を 資本主義自体が制限してしまう、というダブルバインド ( 二重拘束 ) が 資本主義からの脱却を困難にしている という事なのです。
1. しかし、問題なのは、"物としての環境問題" 以前の、"物としての資本主義" です。環境問題が政治を権力闘争から現実的解決問題へと移行させるのは良いとしても、環境問題が極めて資本主義的な問題である事です。ここで資本主義的問題であるというのは、資本主義が惹き起こす環境汚染や気候変動などの危機的事象であるという事 ( それについては本書で述べられているので参照 ) ではなく、資本主義によって惹き起こされる環境問題に取り組む私たちの行動を 資本主義自体が制限してしまう、というダブルバインド ( 二重拘束 ) が 資本主義からの脱却を困難にしている という事なのです。
![]() 2. 資本主義による制限とは私たちに課せらる "物" の価格 です。CO2 排出制限のための技術革新が価格に転嫁されるのは今更言うまでもありませんが、このことの哲学的意味とは何でしょう。マルクス主義的に言うなら、ここには疎外された人間性が、価格や税金などの支払い行動という原理を通じて取り戻される資本主義的主体の転倒的存在があるのですが、この資本主義的主体に与えられる現実的選択は二つしかない、払えるか、払えないか、それだけなのです。
2. 資本主義による制限とは私たちに課せらる "物" の価格 です。CO2 排出制限のための技術革新が価格に転嫁されるのは今更言うまでもありませんが、このことの哲学的意味とは何でしょう。マルクス主義的に言うなら、ここには疎外された人間性が、価格や税金などの支払い行動という原理を通じて取り戻される資本主義的主体の転倒的存在があるのですが、この資本主義的主体に与えられる現実的選択は二つしかない、払えるか、払えないか、それだけなのです。
![]() 3. だから、いくら環境問題に取り組みたくても、生活を圧迫するのなら、当然払わない。この単純な反応行動が環境問題への取り組む主体を抑圧する訳です。人類の生存を脅かしかねない巨大な問題が、生活を守ろうとする個人の日常生活へと収斂し、身動きを取れなくさせている。逆に言うと、この個人の日常生活をスルーして、大きな問題を解決しようとしても、価格の支払い主体である私たちはまず金銭面という物理的限界によって行動を制限される のです。
3. だから、いくら環境問題に取り組みたくても、生活を圧迫するのなら、当然払わない。この単純な反応行動が環境問題への取り組む主体を抑圧する訳です。人類の生存を脅かしかねない巨大な問題が、生活を守ろうとする個人の日常生活へと収斂し、身動きを取れなくさせている。逆に言うと、この個人の日常生活をスルーして、大きな問題を解決しようとしても、価格の支払い主体である私たちはまず金銭面という物理的限界によって行動を制限される のです。
![]() 4. それがエコカーの購入など価格の高い物に対して払う・払わないの選択の自由度が効くものであるのならまだいい ( 余裕があれば買う・なければガソリン車を買う ) のですが、電気・水道などのライフラインのように人間の生活の基盤であるものに対してはほぼ支払う事を拒否出来ないが故に問題は深刻になる。日本における発電量の8割強を占める火力発電をCO2 排出制限のために削減しようとする一方で、震災不安による原子力発電の停止が続く状況は環境面からしたら好ましくとも、そのコスト増を負担するのは最終的に私たち自身に他ならないという資本主義的現実に耐えうるか という事こそ考えなければならない問題なのですね。
4. それがエコカーの購入など価格の高い物に対して払う・払わないの選択の自由度が効くものであるのならまだいい ( 余裕があれば買う・なければガソリン車を買う ) のですが、電気・水道などのライフラインのように人間の生活の基盤であるものに対してはほぼ支払う事を拒否出来ないが故に問題は深刻になる。日本における発電量の8割強を占める火力発電をCO2 排出制限のために削減しようとする一方で、震災不安による原子力発電の停止が続く状況は環境面からしたら好ましくとも、そのコスト増を負担するのは最終的に私たち自身に他ならないという資本主義的現実に耐えうるか という事こそ考えなければならない問題なのですね。
![]() 5. ここで言いたいのは、個人の生活コストを増大させる環境問題は切り捨てるべきだという事ではありません。環境問題はやはり考えられなければならないのですが、それは コストという点で個人の日常生活と短絡的に結びついている。もし個人の日常生活の維持などどうにでもなるだろうなどと考えるのであれば、環境問題は結局の所、旧態依然とした "権力闘争的イデオロギー" としてしか機能しない事になるでしょう。環境問題の解決のためにはコスト負担という個人の日常生活へのしわ寄せは仕方ない …… この恐るべき暗黙の前提は、集団的主体性を最悪の形で回帰させる事になる。経済的に制限された私たち大多数は、問題解決のために動く事すら出来ず、"たんなる大多数" として固定化された存在論的身分に留まるしかなくなる のです。これを無視して環境問題を語っても、それは政治家・企業、富裕層においてのみ活発的な疑似使命感で装われた欲望の対象でしかなくなるでしょう。
5. ここで言いたいのは、個人の生活コストを増大させる環境問題は切り捨てるべきだという事ではありません。環境問題はやはり考えられなければならないのですが、それは コストという点で個人の日常生活と短絡的に結びついている。もし個人の日常生活の維持などどうにでもなるだろうなどと考えるのであれば、環境問題は結局の所、旧態依然とした "権力闘争的イデオロギー" としてしか機能しない事になるでしょう。環境問題の解決のためにはコスト負担という個人の日常生活へのしわ寄せは仕方ない …… この恐るべき暗黙の前提は、集団的主体性を最悪の形で回帰させる事になる。経済的に制限された私たち大多数は、問題解決のために動く事すら出来ず、"たんなる大多数" として固定化された存在論的身分に留まるしかなくなる のです。これを無視して環境問題を語っても、それは政治家・企業、富裕層においてのみ活発的な疑似使命感で装われた欲望の対象でしかなくなるでしょう。
![]() 6. ということは環境問題は、政治的手法・政治的主体に対しては変化を引き起こすものであっても、経済的には私たちが資本主義的イデオロギーを乗り越え不可能にしている "物" なのです。他国へのコストの外部転化という帝国的経済様式は批判にさらされ減少していっても、自国民はそのコスト及び物質的残滓を自らひたすら背負うしかなくなるという悪循環が最も具現化されたものこそ環境問題なのです。そのことを念頭に置くなら、環境問題を解決するためには脱成長経済が必要だとしても、それが資本主義内部で行われるものである限り、脱成長経済のためにはさらなるコストが発生するという "矛盾" が人間に転嫁されてしまう のです。
6. ということは環境問題は、政治的手法・政治的主体に対しては変化を引き起こすものであっても、経済的には私たちが資本主義的イデオロギーを乗り越え不可能にしている "物" なのです。他国へのコストの外部転化という帝国的経済様式は批判にさらされ減少していっても、自国民はそのコスト及び物質的残滓を自らひたすら背負うしかなくなるという悪循環が最も具現化されたものこそ環境問題なのです。そのことを念頭に置くなら、環境問題を解決するためには脱成長経済が必要だとしても、それが資本主義内部で行われるものである限り、脱成長経済のためにはさらなるコストが発生するという "矛盾" が人間に転嫁されてしまう のです。

![]() CHAPTER4 資本主義と矛盾、あるいは資本主義の中の矛盾 ……
CHAPTER4 資本主義と矛盾、あるいは資本主義の中の矛盾 ……
![]()
![]() 1. ここで寄り道を少ししてみましょう。マルクス主義的に考えると、資本主義における "矛盾" は、資本主義を止揚して次の段階に移行させるという事になるのですが、このことは矛盾という概念が資本主義を貫くほどの作用を持つ "特権的歴史法則 ( 唯物史観 )" の1要素である事を示しています ( もうこういったマルクス主義概念は古臭すぎて本書で言及される事もない )。つまり、矛盾概念を含む弁証法を基盤とする唯物史観は資本主義の外部に存在する客観的的法則であるかのように扱われているという事なのですが、そのように客観的概念であるかのように見えるのは、矛盾という概念がシステム全体性を解体構築させる、つまり、止揚させるかのような特殊な部分という意味での理解されているからに他なりません。資本主義というシステムの全体性が閉じられ自足してしまうのを、"矛盾という部分性" がシステムの均衡を突き崩し、新たなるシステム ( 共産主義 ) へと向かわせる。この全体の中の異質な部分に与えられる概念こそ、ヘーゲルの弁証法的思考から参照・挿入された止揚なのですが、物事の運動の原動力となるものが物事に対立する否定的なものというその弁証法的思考を今一度、原理的に考えてみましょう。
1. ここで寄り道を少ししてみましょう。マルクス主義的に考えると、資本主義における "矛盾" は、資本主義を止揚して次の段階に移行させるという事になるのですが、このことは矛盾という概念が資本主義を貫くほどの作用を持つ "特権的歴史法則 ( 唯物史観 )" の1要素である事を示しています ( もうこういったマルクス主義概念は古臭すぎて本書で言及される事もない )。つまり、矛盾概念を含む弁証法を基盤とする唯物史観は資本主義の外部に存在する客観的的法則であるかのように扱われているという事なのですが、そのように客観的概念であるかのように見えるのは、矛盾という概念がシステム全体性を解体構築させる、つまり、止揚させるかのような特殊な部分という意味での理解されているからに他なりません。資本主義というシステムの全体性が閉じられ自足してしまうのを、"矛盾という部分性" がシステムの均衡を突き崩し、新たなるシステム ( 共産主義 ) へと向かわせる。この全体の中の異質な部分に与えられる概念こそ、ヘーゲルの弁証法的思考から参照・挿入された止揚なのですが、物事の運動の原動力となるものが物事に対立する否定的なものというその弁証法的思考を今一度、原理的に考えてみましょう。
![]() 2. 間違っても、資本主義などのシステムを説明するのに、弁証法的思考が古い時代の遺物であり現代では説得力がないなどというシニカルな態度をとるべきではありません。問題なのは、弁証法的思考のシステム論への適合性などではなく、不平等な資本主義というシステムの中には自らを解体構築させていくものが含まれているのかどうか、という事なのです。資本主義の諸々の場面において発生する矛盾が、システムを超える運動を産み出す外部的普遍性を備えているのか、それとも、資本主義を修正的に変更してシステムを維持する予定調和的なものに過ぎないのか、という矛盾概念の存在論的地位に関わるものです。
2. 間違っても、資本主義などのシステムを説明するのに、弁証法的思考が古い時代の遺物であり現代では説得力がないなどというシニカルな態度をとるべきではありません。問題なのは、弁証法的思考のシステム論への適合性などではなく、不平等な資本主義というシステムの中には自らを解体構築させていくものが含まれているのかどうか、という事なのです。資本主義の諸々の場面において発生する矛盾が、システムを超える運動を産み出す外部的普遍性を備えているのか、それとも、資本主義を修正的に変更してシステムを維持する予定調和的なものに過ぎないのか、という矛盾概念の存在論的地位に関わるものです。
![]() 3. この問題を考える上で、参照したいのは、精神分析家 ジャック・ラカン の提唱した概念、現実界 ( 象徴界との関係性における ) です。ただし、精神分析理論のそれではなく、スラヴォイ・ジジェクによって急進化された政治理論としての現実界です。人間の経験において発生する超越的なものとしての 現実界 と、それとの危険な遭遇を避けるために組織化された全体性としての 象徴界 ( 言語活動を含めた ) という関係性 を、矛盾とそれを抱え込むシステムの関係性 と対比させるのは無駄な事ではないでしょう。
3. この問題を考える上で、参照したいのは、精神分析家 ジャック・ラカン の提唱した概念、現実界 ( 象徴界との関係性における ) です。ただし、精神分析理論のそれではなく、スラヴォイ・ジジェクによって急進化された政治理論としての現実界です。人間の経験において発生する超越的なものとしての 現実界 と、それとの危険な遭遇を避けるために組織化された全体性としての 象徴界 ( 言語活動を含めた ) という関係性 を、矛盾とそれを抱え込むシステムの関係性 と対比させるのは無駄な事ではないでしょう。
![]() 4. ここでのポイントは、象徴界はその網の目を閉じて完全に閉域化する事は出来ないという事です。もし完全に閉じてしまえば象徴界はそれを作動させるための足場が無くなってしまう。その足場とは、人間主体の空虚な立ち位置です。人間にとって最も究極のトラウマとは 自分の存在 に他ならないのですが、この偶然で無意味な出来事としての "現実界との遭遇" こそ人が避けようとするもの なのです。象徴界とは、この現実界との遭遇を緩和し主体が自らの位置を常に超越的なものとして仮想化する ( 自分の根源に触れないでおくための意識操作 ) 行為の具現化されたものだといえます。人間が自己疎外したものとして象徴界は存在する。そこに関わる事によって人間は自らの存在というトラウマを抑圧する。しかし、象徴界の中の欠如である現実界 ( トラウマ ) は回帰してくるのです。
4. ここでのポイントは、象徴界はその網の目を閉じて完全に閉域化する事は出来ないという事です。もし完全に閉じてしまえば象徴界はそれを作動させるための足場が無くなってしまう。その足場とは、人間主体の空虚な立ち位置です。人間にとって最も究極のトラウマとは 自分の存在 に他ならないのですが、この偶然で無意味な出来事としての "現実界との遭遇" こそ人が避けようとするもの なのです。象徴界とは、この現実界との遭遇を緩和し主体が自らの位置を常に超越的なものとして仮想化する ( 自分の根源に触れないでおくための意識操作 ) 行為の具現化されたものだといえます。人間が自己疎外したものとして象徴界は存在する。そこに関わる事によって人間は自らの存在というトラウマを抑圧する。しかし、象徴界の中の欠如である現実界 ( トラウマ ) は回帰してくるのです。
![]() 5. 資本主義におけるいかなる矛盾も、哲学的には自己疎外された人間性が物として物象化され "主体を呑み込みかねないシステム" として回帰する時に生じると考えられるでしょう。原理的にそうであるからこそ、資本主義における被害性の対象が人間主体である事の現実界は際限のないものとして経済的に切り捨てられてしまう。環境問題のためには、そのためのコストが私たちにいくら課せられようとも仕方がないという事になりかねない ( 払ってもうらうしかない ) …… 。ここから考えられることは、かつてのマルクス主義が、資本主義における矛盾を次の共産主義の段階へと推し進める歴史的法則として見なしたのと同じように、"環境問題が資本主義を解体構築する契機としての矛盾が具現化されたもの" と無意識的に信じている という事です。つまり、環境問題は資本主義の内部には収まり切れない歴史的事実であり、これを解決するには資本主義を変革するしかないという訳です。
5. 資本主義におけるいかなる矛盾も、哲学的には自己疎外された人間性が物として物象化され "主体を呑み込みかねないシステム" として回帰する時に生じると考えられるでしょう。原理的にそうであるからこそ、資本主義における被害性の対象が人間主体である事の現実界は際限のないものとして経済的に切り捨てられてしまう。環境問題のためには、そのためのコストが私たちにいくら課せられようとも仕方がないという事になりかねない ( 払ってもうらうしかない ) …… 。ここから考えられることは、かつてのマルクス主義が、資本主義における矛盾を次の共産主義の段階へと推し進める歴史的法則として見なしたのと同じように、"環境問題が資本主義を解体構築する契機としての矛盾が具現化されたもの" と無意識的に信じている という事です。つまり、環境問題は資本主義の内部には収まり切れない歴史的事実であり、これを解決するには資本主義を変革するしかないという訳です。
![]() 6. しかし、精神分析が示したように、象徴界が人間の存在という現実界 ( トラウマ ) を避けるために出現したのであれば、環境問題とは、人間の存在 ( マルクス主義的、社会学的、に言うならば、人間の関係性 ) という現実界を見えなくさせる形式でその危機的事実に溶け込んだ構造的なものだ ともいえるでしょう。それはシステム内部の欠如という穴から姿を見せる外部であっても、システムの近傍・裏面に付着する構造的なもの でしかなく、資本主義の次の段階への移行を予感させる "歴史的必然性" は含まれていない のです。それは危機的な問題ですが、残念ながら、資本主義を壊しながらも同時に生きながらえさせる "システムの延命契機" となってしまっている。どれだけ客観的に危険な問題でも、それに対する効果的な実務アプローチが巨大でなければ意味がない ( そういう意味ではコンビニ・スーパーでのレジ袋有料化などはどうしようもない ) のだとすれば、その方法は現資本主義システムに沿ったものでなければ物理的に困難でしょう。その心理的帰結は既に先取りされていて、資本主義を肯定する人であれ否定する人であれ、環境問題を取り組む上で人間主体に無制約にコストが掛かる事の "現実的意味" を気にかけない事態が政治的に生じてしまっている。
6. しかし、精神分析が示したように、象徴界が人間の存在という現実界 ( トラウマ ) を避けるために出現したのであれば、環境問題とは、人間の存在 ( マルクス主義的、社会学的、に言うならば、人間の関係性 ) という現実界を見えなくさせる形式でその危機的事実に溶け込んだ構造的なものだ ともいえるでしょう。それはシステム内部の欠如という穴から姿を見せる外部であっても、システムの近傍・裏面に付着する構造的なもの でしかなく、資本主義の次の段階への移行を予感させる "歴史的必然性" は含まれていない のです。それは危機的な問題ですが、残念ながら、資本主義を壊しながらも同時に生きながらえさせる "システムの延命契機" となってしまっている。どれだけ客観的に危険な問題でも、それに対する効果的な実務アプローチが巨大でなければ意味がない ( そういう意味ではコンビニ・スーパーでのレジ袋有料化などはどうしようもない ) のだとすれば、その方法は現資本主義システムに沿ったものでなければ物理的に困難でしょう。その心理的帰結は既に先取りされていて、資本主義を肯定する人であれ否定する人であれ、環境問題を取り組む上で人間主体に無制約にコストが掛かる事の "現実的意味" を気にかけない事態が政治的に生じてしまっている。
![]() 7. この回帰してくる疎外された人間性、この無定型であるが故に、あらゆる形象、主体、対象、となりうる人間が、"コストを背負う / 背負せられる"、だけの何ら主導権を持たない経済的対象 ( それはもう活動的主体ではない ) である事が止揚されないからこそ資本主義は生き延び続ける のです。脱成長経済が旧来の脱成長派やSDGs とは違い、生産や労働における変革を唱えるのは一見正しいのですが、一体 "誰" に対して、変革しろと言っている のでしょう。労働者が自分が働く会社の社長や上層部に対して変革のための労使交渉をしろと言うのでしょうか。そういう労働者の環境改善の取り組みという行為自体が社会的評価の対象として重視されるようになった近年では、それは珍しいことではありません ( 当然そういう取り組みに関心を示さない会社も以前としてありますが )。ただし、それが会社の利潤追求を損ねない限りであり、労働者がその会社の方針に従う限り、であるという極めて資本主義的枠組みを前提としたものでしかないのです。つまり、生産や労働の変革が出来る会社というのは、それだけの事が出来る余裕を持つ会社、それだけの利益を出している会社、であるという事なのは言うまでもありませんね。
7. この回帰してくる疎外された人間性、この無定型であるが故に、あらゆる形象、主体、対象、となりうる人間が、"コストを背負う / 背負せられる"、だけの何ら主導権を持たない経済的対象 ( それはもう活動的主体ではない ) である事が止揚されないからこそ資本主義は生き延び続ける のです。脱成長経済が旧来の脱成長派やSDGs とは違い、生産や労働における変革を唱えるのは一見正しいのですが、一体 "誰" に対して、変革しろと言っている のでしょう。労働者が自分が働く会社の社長や上層部に対して変革のための労使交渉をしろと言うのでしょうか。そういう労働者の環境改善の取り組みという行為自体が社会的評価の対象として重視されるようになった近年では、それは珍しいことではありません ( 当然そういう取り組みに関心を示さない会社も以前としてありますが )。ただし、それが会社の利潤追求を損ねない限りであり、労働者がその会社の方針に従う限り、であるという極めて資本主義的枠組みを前提としたものでしかないのです。つまり、生産や労働の変革が出来る会社というのは、それだけの事が出来る余裕を持つ会社、それだけの利益を出している会社、であるという事なのは言うまでもありませんね。

![]() CHAPTER5 労働から日常へ
CHAPTER5 労働から日常へ
![]()
![]() 1. そのような脱資本主義的改革を進めるための主体は "誰" であるのか、この問いが行き着く先について考える必要があるでしょう。労働者である事の "当事者性" が脱資本主義的改革のための重要な要素であると思うのならそれは思い違いであるかもしれない。自分たちの生活を成り立たせている資本主義、というより 実体的な会社組織 ( これを法人資本主義という人もいる ) が給与を払ってくれることで生活が成り立つのを労働者自身が身に染みて分かっている という現実、これを考えずに環境問題を契機にして脱資本主義を図ろうとしても、結局、終わりなき日常に回収されてしまうでしょう。かつての東北大震災で起きた原発事故に対する批判が縮小していったように。
1. そのような脱資本主義的改革を進めるための主体は "誰" であるのか、この問いが行き着く先について考える必要があるでしょう。労働者である事の "当事者性" が脱資本主義的改革のための重要な要素であると思うのならそれは思い違いであるかもしれない。自分たちの生活を成り立たせている資本主義、というより 実体的な会社組織 ( これを法人資本主義という人もいる ) が給与を払ってくれることで生活が成り立つのを労働者自身が身に染みて分かっている という現実、これを考えずに環境問題を契機にして脱資本主義を図ろうとしても、結局、終わりなき日常に回収されてしまうでしょう。かつての東北大震災で起きた原発事故に対する批判が縮小していったように。
![]() 2. つまり、環境問題は、資本主義の過剰性を反省させる強力な要素であるとしても、資本主義に対する革命を、資本主義内部における修正改革、へと私たちの行動を制限させるものでしかない ( コスト負担によって ) のです。人間の存在における倫理や道徳に訴える行動は、インパクトがあっても、永続的であることは出来ない。それは資本主義的日常に負けてしまう のです。
2. つまり、環境問題は、資本主義の過剰性を反省させる強力な要素であるとしても、資本主義に対する革命を、資本主義内部における修正改革、へと私たちの行動を制限させるものでしかない ( コスト負担によって ) のです。人間の存在における倫理や道徳に訴える行動は、インパクトがあっても、永続的であることは出来ない。それは資本主義的日常に負けてしまう のです。
![]() 3. とするのなら、ここで私たちが採るべき戦略は、資本主義を倫理的に否定する事ではなく、日常圏域に入ってくる政治経済的諸事項において徹底的にコストを下げるという 疑似資本主義的行動を欲望原理にする事 です。それは 私たちに負担させられる "資本主義的コスト" を "物の政治" へと移行させる、つまり、資本主義を脱-経済的なものへと政治化させる のです。政治に興味がなくとも、私たちの負担するコストの増加は、私たちの政治的関心を高める事になる。日常生活における資本主義的負担が政治的行動の原理となるという簡潔性は、デモなどの一時的高揚よりも地味だが永続的な行動の動機となり続けるでしょう。
3. とするのなら、ここで私たちが採るべき戦略は、資本主義を倫理的に否定する事ではなく、日常圏域に入ってくる政治経済的諸事項において徹底的にコストを下げるという 疑似資本主義的行動を欲望原理にする事 です。それは 私たちに負担させられる "資本主義的コスト" を "物の政治" へと移行させる、つまり、資本主義を脱-経済的なものへと政治化させる のです。政治に興味がなくとも、私たちの負担するコストの増加は、私たちの政治的関心を高める事になる。日常生活における資本主義的負担が政治的行動の原理となるという簡潔性は、デモなどの一時的高揚よりも地味だが永続的な行動の動機となり続けるでしょう。
![]() 4. 特に、将来的に各家庭のおける支出の増加になりかねない地域ごとの電気・水道・ガスなどのライフラインの在り方 ( その所有者の変化・燃料費の変動・設備の維持等 ) などについては市民が共有できる知識化・媒体化が必要になるし、それは各自治体の市町村との協力なしには築けません。だから、そのような公的な物は、逆説的に資本主義的コストの面から興味を持たれる事で共有の意味合いが議論されるようになる。ただ、共有する事の道徳的価値を説いても、そこから脱資本主義的行動の実践を引き出すことは難しい。真に共有されるべきは、公的機関と私たち市民による行政行動であり、特に地方自治行政についての知識共有化は市民をコスト的に政治に関わらせる上で必要になる ( ライフラインだけではない政治的諸事項に対する知識化の拡がりは市民の視点を強化する )。
4. 特に、将来的に各家庭のおける支出の増加になりかねない地域ごとの電気・水道・ガスなどのライフラインの在り方 ( その所有者の変化・燃料費の変動・設備の維持等 ) などについては市民が共有できる知識化・媒体化が必要になるし、それは各自治体の市町村との協力なしには築けません。だから、そのような公的な物は、逆説的に資本主義的コストの面から興味を持たれる事で共有の意味合いが議論されるようになる。ただ、共有する事の道徳的価値を説いても、そこから脱資本主義的行動の実践を引き出すことは難しい。真に共有されるべきは、公的機関と私たち市民による行政行動であり、特に地方自治行政についての知識共有化は市民をコスト的に政治に関わらせる上で必要になる ( ライフラインだけではない政治的諸事項に対する知識化の拡がりは市民の視点を強化する )。
![]() 5. 家庭では当たり前の節約が国家や地方自治体では予算が何の遠慮もない行使に取って代わられる飛躍を、市民の日常圏域に接続し直す事によって壊さなければなりません。そうしなければ大文字の問題 ( 環境問題、資本主義等 ) の名目の下で私たちは永遠に黙って "コストを負担するだけの資本主義的主体 ( マウリツィオ・ラッツァラートなら "借金人間" というだろう )" であり続けるしかない。人間関係・派閥関係によらない日常の経済コストを契機とする "物の政治化" は地方自治においてこそその可能性を強め、それはやがて地域の統合・再編問題を経由して市民がより政治に関わらざるを得ない状況を生み出していくでしょう。
5. 家庭では当たり前の節約が国家や地方自治体では予算が何の遠慮もない行使に取って代わられる飛躍を、市民の日常圏域に接続し直す事によって壊さなければなりません。そうしなければ大文字の問題 ( 環境問題、資本主義等 ) の名目の下で私たちは永遠に黙って "コストを負担するだけの資本主義的主体 ( マウリツィオ・ラッツァラートなら "借金人間" というだろう )" であり続けるしかない。人間関係・派閥関係によらない日常の経済コストを契機とする "物の政治化" は地方自治においてこそその可能性を強め、それはやがて地域の統合・再編問題を経由して市民がより政治に関わらざるを得ない状況を生み出していくでしょう。
![]()

〈 関連記事 〉