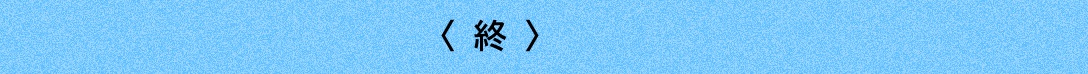映画 『 地獄の黙示録 ( Apocalypse Now ) 』
監督 フランシス・フォード・コッポラ ( Francis Ford Coppola : 1939~ )
公開 1979年
脚本 ジョン・ミリアス ( John Milius : 1944~ )
フランシス・フォード・コッポラ
出演 マーロン・ブランド ( Marlon Brando : 1924~2004 ) カーツ大佐
マーティン・シーン ( Martin Sheen : 1940~ ) ウィラード大尉
ロバート・デュバル ( Robert Duvall : 1931~ ) キルゴア中佐
フレデリック・フォレスト ( Frederic Forrest : 1936~ ) ジェイ・“シェフ”・ヒックス
サム・ボトムズ ( Sam Bottoms : 1995~2008 ) ランス・B・ジョンソン
ローレンス・フィッシュバーン ( Laurence Fishburne : 1961~ ) タイロン・“クリーン”・ミラー

第1章 ジョン・ミリアスとフランシス・F・コッポラ

▨ 『 地獄の黙示録 』、 この製作過程における幾つものアイディアの挿入と脚本の改変によって繋ぎ合わされた作品が注目されたのは奇妙な感じだった。 監督のコッポラをして何を主題にして撮っているのか途中で分からなくなったと言わしめた作品がカンヌ映画祭のパルムドールを受賞 ( 1979年 ) してしまったのですから。 それは、 争いの絶えない国家でどこかの政権が樹立されるまで主導権の在処が不安定な様に、 コッポラがこの映画をコントロールするのにどれ程の苦労を味わされたかを察する事が出来る事態だったといえるでしょう。
▨ コッポラが映画化の権利を得る前から、 ジョセフ・コンラッド ( Joseph Conrad : 1857~1924 ) の小説 『 闇の奥 ( 1902 ) 』 を基にしてアイデアを練っていた ( 映画用の脚本を書き始めたのはコッポラが権利を得てから ) ジョン・ミリアスを発端として、 この映画は始まった。 なので基本的にはこの作品はジョン・ミリアスの脚本を骨子としつつコッポラの芸の細かい改変によって出来上がったのですね。 実際に、 この映画は『 闇の奥 』を基本モチーフにしているだけでなく、 原題の『 Apocalypse Now 』、 BGMのドアーズ『 The End 』、 爆撃シーンでのワーグナー『 ワルキューレの騎行 』、 そしてキルゴア中佐のサーフィンシーン、 などの多くの映画ファンの関心を惹いたアイデアが実はコッポラではなくジョン・ミリアスによるのは今日では知られている所です。
▨ しかし、 もし彼がこの映画の監督だったとしたら、 コッポラほどの重厚さを産み出す事は出来なかったのは間違いないでしょう。 ジョン・ミリアスが自分で監督するより、 コッポラの方がジョンのアイデアを生かす演出が出来た事は、 ジョンが監督した映画を観た人であれば納得するはずです ( *1 )。 ジョン・ミリアスの力量では、 特にジョセフ・コンラッドの 『 闇の奥 』 でも見せ場のひとつでもあるカーツが死ぬ場面の緊張感を再現出来たかどうかは怪しい。 観客にとっても分かりやすい戦争シーンが満載の前半よりも、 いまいちピンとこなくて人気の無い後半のシーンはコッポラでさえ苦労した跡が伺えますからね。
( *1 )
ジョン・ミリアスによるB級戦争映画についてはこちら。 もっとも彼の中ではB級などではなく、 戦争大作を作ったつもりなのでしょうけど。

第2章 原作を必要とする映画、そしてその逆も ……

▨ この記事では、 そのカーツの死をクライマックスとするシーンを中心に考えていきます。 正直、 コッポラの演出は上手くいっているというよりは、 説明足らずで分かりにくいでしょう。 それは映画と原作の小説との形式的違いがその一因でもあるのです。 つまり、 映画は 客観的視線によって支えられるイマージュ であるのに対して、 コンラッドの 『 闇の奥 』 が最も面白くなるのは、 マーロウの 1人称による圧倒的独白 が続く所であり、 それは 主体の中の内的時間とでもいうべきものであって、 可視化されたイマージュには還元されない何か であるのです。 仮にそれを可視化しようとすれば、 "闇" の中でマーロウの声だけが延々と続くという観客には耐え難い結果になるでしょう ( *2 )。 という事で、 クライマックスのシーンについてコッポラは明確な解釈を提示する事が出来ていないので、原作を解釈する事によって補完する必要があります。 それは 映画が原作を必要とするという一方的な関係性ではなく、 原作も映画によって新たな生命を得るという双方性 でもあり、 極めてヴァルター・ベンヤミン的な哲学テーマ ( *3 ) なのです。
▨ なぜこんな事を書くかと言うと、 現在ではポストコロニアル批評による植民地批判の観点でのみコンラッドの 『 闇の奥 』 が語られてしまう傾向 ( 原住民への植民地的主義的描写がいくつかあるのは確かですが ) が強く、 そこでは "小説的なもの" が政治的なものが支配する空間に閉じ込められているからです。 そのような空間では小説はそれ自体を楽しむ事が出来ない、 つまりベンヤミン的視点では 『 闇の奥 』 は新たな生命を得る事が出来ないという事であり、 やがては消え行く傾向に呑まれていく。 そういうベンヤミン的視点に立った時、 『 地獄の黙示録 』 は製作者達の意図を超えて、 コンラッドの 『 闇の奥 』 を現代に甦らせる映画として興味深いものなのです。 ここに、 原作によって映画の解釈を補完する事の意義があるのですね。
( *2 )
この 客観的視線によるイマージュ と 主体の内的時間としての独白 こそが、映画と小説との形式的差異を表す対立テーゼだと言えるでしょう。 小説の1人称による独白を映像化しようとする試みはほとんど失敗してしまう。 この形式的差異を考慮する事のない観客にとっては全く面白みを感じないという訳ですね。 その失敗例のひとつが、ジム・トンプスン ( Jim Thompson : 1906~1977 ) によるノワール小説 『 おれの中の殺し屋 ( 1952 : The Killer Inside Me ) 』 を映画化した マイケル・ウインターボトム ( Michael Winterbottom : 1961~ ) の 『 キラー・インサイド・ミー 』 です。 主人公の内的独白の "声" がほぼ失われているものの、サウンドトラックの "音楽性" がそれを補っているこの奇妙な映画については以下の記事を参照。
( *3 )
哲学者 ヴァルター・ベンヤミン ( Walter Benjamin : 1892 ~ 1940 ) は、 『 複製技術時代の芸術 』 で "オリジナル" の視点から "複製品" について語り ( これをテーゼ A とします )、 『 翻訳者の使命 』 では "翻訳 ( 複製品 )" の視点から "原作 ( オリジナル )" について語っている ( これをテーゼ B とします )。 興味深いことに、A と B では視点が逆になっているのです。
テーゼ A では、オリジナルが大量工業化社会における複製化に抗う事が出来ないものの、オリジナルは複製品によってこそ、その中に新しい生命を得る ( より多くの人の目に触れる ) とされる。
テーゼ B では、翻訳が原作に忠実である事が翻訳者に課せられた使命とされる。ただし、この忠実性さというのが問題で、ベンヤミンは決して読者に読みやすく翻訳する事が原作への忠実さであるなどという常識的な主張をしている訳ではないのです。 むしろ彼は逐語的な翻訳を望んでいて、読みやすさという視点は最初から廃棄されている。それについて解釈するには、 ジャック・デリダ ( Jacques Derrida : 1930~2004 ) の 『 バベルの塔 』 を参考にしつつ、多くの言語が存在する事自体が言語間の根本的な翻訳不可能性を示しているのを考慮に入れる必要がある。 つまり、逐語的翻訳で明らかになる読みづらさこそが、根本的に翻訳不可能な言語間の隔たりを乗り越えて、 原作が新しい生命を得ようとする際の "唯物的振舞い" である と解釈しなければならないのです。
以上の A と B を踏まえて、ここで避けるべき過ちは、テーゼ B に依拠して映画は原作に忠実であるべきだという結論です。 そうではなく、少なくとも1人称形式が多用される小説と映画では、その存在形式が違うのだから ( 視線によって支えられるイマージュ と 主体の内的時間としての独白 との違い ) 、根本的に原作に忠実である事が出来ない、いや、そこでは忠実さという考え方自体に意味が無い。 むしろ、映画の場合は、翻訳と違って 原作を 自由に解釈すべき なのです。 その結果、生じる原作との隔たり、軋轢、裏切り、などが根本的に移行が不可能な映画と小説との媒体的差異を明らかにし、それを乗り越えて出来た映画にこそ、小説の新しい命が宿ると考えられるのです。
つまり、原作 ( 小説 ) の映像化という紋切り型 ( 商業的意味での ) は、複製的な範疇に収まるものなの ( テーゼ A ) ですが、異なる媒体への移行作業である映画化においては解釈の自由性が必要となる のですね。 これこそ映画におけるテーゼ B の変形ヴァージョンとしての新しいテーゼ C 、"移行媒体物 ( 映画 )" の視点から "原作 ( オリジナル )" について考える というものなのです。

第3章 原作から微妙にずれるコッポラの解釈

▨ カーツが地獄の恐怖について語りながら死ぬシーンこそ、 この映画のクライマックスと言えるでしょう。 以下 ( 1 ~ 5. ) は原作にはないカーツのセリフ。 地獄の恐怖と向き合い、 それをどうにかしたいという思いが吐露されている。


▨ そして死の直前の有名な "地獄だ。地獄の恐怖だ" のセリフ。 原作では "The horror! The horror! " ( *4 )。

▨ さて、 ここで原作を知らずに映画を観た人は、 カーツは死ぬ事を恐れているのだろうかと思うでしょう、 ウィラード大尉が軍の命令によってカーツを殺しに来た事を考え合わせれば。 原作を読んだ人ならば、 そうではない事が分かるのですが、 実はカーツが死を恐れているという解釈は間違っていないのです、 少なくとも映画に関しては。 なぜなら、 それは コッポラ自身が原作から "微妙に" 逸れた解釈を提示した結果 だからです。 端的に言うと、 コッポラは "死" と "地獄" を同一視している のです。 恐れるべきものは "死" なのであり、 それはジャングルの奥地で増幅され、 カーツを狂わせたとコッポラは考えている。 だから "王殺しという神話的概念" を持込む事によって、 ジャングルの王であるカーツと王を殺しに来たウィラードとを "死" で結びつける三角関係によって話を進めるという脚色を行った訳です。
▨ そして、このコッポラの脚色は、かなり凝ったものになっていますね。 彼はコンラッドの 『 闇の奥 』 を骨子とするというジョン・ミリアスのアイデアに、同じくコンラッド繋がりで T.S.エリオット ( T.S. Eliot : 1888~1965 ) を接続する事によって表面上は話の流れに一貫性を持たせようとしているのです。 20世紀モダニズムの詩人である T.S. エリオットは、詩作においてコンラッドを参照していた 事で有名なのですが、コッポラはその事を上手く利用している。 エリオットを導入する事によって、彼が参照していたコンラッド、 ジェームズ・フレイザー ( James Frazer : 1854~1941 ) の 『 金枝篇 』、 ジェシー・ウェストン ( Jessie Weston : 1850~1928 ) の 『 祭祀からロマンスへ ( From Ritual to Romance : 1920 ) 』 を画面中に一気に登場させ、王殺しの脚色を確定させるという教養的荒技を出すのです ( *5 )。
▨ カーツが死に至るシークエンスにおいては皆、 コッポラの教養に惑わされて引用物に注目する事に留まり、 それ以上解釈する事を忘れてしまう ( どれほど多くの批評がそうである事か ) のですが、 王殺しの脚色はウィラードがカーツの王国に留まらずに外部に戻るという話によって破綻しているという事に注意すべきでしょう。 なぜなら王殺しの神話は王国の再建・復活というモチーフが必須なのですが、 ウィラードはそういう事に興味を示さないし、 そもそもカーツは "爆弾を投下してすべてをせん滅せよ" と言っているのです。
▨ そうすると、 ここから読み取るべきは、 王殺しの脚色はカーツの死にアクセントを付けるためのアリバイに過ぎず、 コッポラは、 カーツに忍び寄る死の実存主義的恐怖を描いた というのが本当の所でしょう。 王国を築いたカーツは、 "死" というものが自分の肉体のみならず、 王国を含めた自分の世界そのものの滅亡である事を望んでいた。 それを実現するのが眼前のアメリカ軍の爆撃なのであれば、 コッポラは無慈悲な戦争の中で省みられない個人の世界を、死の実存主義に取り憑かれたカーツを通して浮かび上がらせた と言えるでしょう。
( *4 )
この "The horror! The horror! " は現在、日本語訳の最新版である光文社古典新訳の 『 闇の奥 』( 2009 ) では "恐ろしい! 恐ろしい!" となっている ( p171 )。 この形容詞的翻訳では、クルツ自身の恐怖の心情を表していると受け止められかねないので、この部分に関しては中野好夫による訳 "地獄だ! 地獄だ!" ( 岩波文庫 1958年 ) の方が適切でしょう。
なぜならクルツは死の間際で、 死ぬ事の恐怖を "感じた" のではなく、 彼が生前から生活してきたジャングルの中で漠然と感じた闇を今まさに "見た" という事を訴えているからです。 彼は "地獄を目撃した" と言っている のですね。 そうすると "The horror! The horror!" は素直に名詞的に "恐怖だ! 恐怖だ!" と訳した方がいいのです。 とはいえ、 光文社古典新訳版の黒原敏行の訳はこれまでの先人の業績も踏まえたものになっているので現状ではこれが妥当なのかなと思います。
( *5 )
コッポラはカーツにエリオットの詩 『 うつろな人々 』 を朗読させているのですが、その 『 うつろな人々 』 では 『 闇の奥 』 の一節 "クルツの旦那 ー 死んだよ" ( 光文社古典新訳版 p.172 ) が引用されている。 ここでコッポラは "入れ子構造" を導入するというちょっとした遊びを披露しているのですね。 それはつまり、『 闇の奥 』 の後年に書かれた 『 うつろな人々 』 を、『 闇の奥 』 を原作とする 『 地獄の黙示録 』 というさらに後年の映画において導き入れる事によって、『 闇の奥 』 と 『 うつろな人々 』 を 同時代で遭遇させている 訳です。

第4章 映画から原作へ …… クルツの真実

▨ さて先程、 コッポラの解釈は、 カーツは死を恐れていて "死" と "地獄" を同一視するものだが原作は違うと言いました。 そこではクルツ ( ここでは映画ではカーツ、 原作ではクルツというように既存の呼び方に倣っている ) は死の間際において絶望こそするものの、 明晰さを保ちつつ決して死を恐れてはいないのです。 この意味で ( *4 ) で述べるように、 クルツの最後のセリフ "The horror! The horror! " は "恐怖だ! 恐怖だ!" とする方が適切でしょう。 クルツが、死の間際の深淵の中で覗き見た "恐怖" とは自分が死んで還っていく無の世界などではなく、 それどころか、人間の存在がそこから産まれる "闇の胎動" だったのです。 人間の形象などはまだあるはずもなく、そこから何かが産まれるであろう予兆としての鼓動が闇に響き渡る幻想を、クルツは明晰に "恐怖" と呼んだ のですね。 『 闇の奥 』 をかつての植民地支配への批判の為の "資料" としてしか ( 小説としてではなく ) 読めない近年のポストコロニアル的批判では、 この解釈 ( 闇の胎動 ) について考える事は出来ないでしょう ( エドワード・サイードでさえ )。
▨ 以下はクルツの事を語るマーロウ ( 映画ではウィラード役に当る ) の独白。
俺も深淵を覗き込んだことがある人間だから、クルツのあの眼差しの意味はよくわかる。彼には蝋燭の炎が見えなかったが、その眼は宇宙全体が見えるほど大きく見開かれ、闇の中で鼓動するすべての心臓を見通せるほど鋭かった。彼はいっさいをまとめあげ ー 審判をくだした。『恐ろしい!』と。
光文社古典新訳版 p.173 ~ 174
俺が一番よく憶えているのは俺自身が死にそうになった時のことじゃない ー 眼の前が何も形をなさない灰色一色になって、肉体的痛みがみなぎり、もうこの痛みを含めて、どうせ何かも儚いものだと、生きる努力を無造作に投げてしまう境地じゃない。違う! 俺はどうやらクルツが死に際に達した境地を経験してしまったようなんだ。
光文社古典新訳版 p.174
俺としては、自分がもう少しで口にするところだった人生最後の言葉は、生きる努力を無造作に投げてしまう言葉ではなかったはずだと考えたいところだ。そんなものよりは、クルツの囁きのほうがいい ー ずっといい。あれは一つのことをちゃんと述べていた。数知れない敗北と、恐ろしい行為の数々と、忌まわしい欲望充足という代償によって得られた精神的勝利ではあったが、ともかく一つの勝利だった!
光文社古典新訳版 p.174 ~ 175
▨ コンゴの奥地のジャングルは人間存在の源泉の闇と共鳴して、クルツの中に正体不明の無意識的衝動として彼を刺激していた。 おそらく、 これこそがクルツの真実であり、 彼に魅了されたマーロウの真実でもあるのです。 最後まで闇の正体を見定めようとしていたクルツの言動を見ると、このコンラッドの 『 HEART OF DARKNESS 』 の邦題は 『 闇の心臓 』 と "逐語的に" 訳す方が相応しいと言えるかもしれません ( 商業的には、今更無理でしょうけど )。
それからクルツは、『 ああ、しかし私はまだこれからお前の心臓を絞りあげてやるからな!』と、見えない魔境に向かって声をあげた。
光文社古典新訳版 p.169